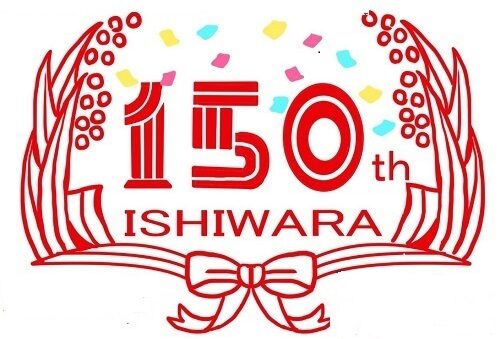さて8月18日(月)12:00~の「やわらか熊谷~僕らがつなぐ物語」は?
第46回「関東一の祇園 熊谷うちわ祭3」をお届けします。
ゲストはうちわ祭といえばこの方 熊谷山車屋台祭研究会会長 新島章夫さんです。「関東一の祇園熊谷うちわ祭」このテーマも第3弾となります。今年のうちわ祭のこと、まだまだ聞けてない伝説、お祭りが終わって1ヶ月、来年のうちわ祭に向けてお話を聞きます。どうぞお楽しみに!
熊谷うちわ祭の第3弾、新島章夫さんに聞く祭りの魅力
⏰月曜日 2025.08.18 12:00 · 54mins
文字起こし
Navi 時刻は12時を回りました。AZ熊谷6階FMクマガヤYZコンサルティングスタジオからお送りします。月曜日のお昼は梅林堂提供やわらか 熊谷僕らがつなぐ物語「第46回関東一の祇園、熊谷うちわ祭3」ということで、第3弾になりました。さあ、うちわ祭りといえば、今日のゲストはこの人熊谷山車屋台祭研究会会長の新島章夫さんです。
新島 こんにちは。ご無沙汰してました。よろしくお願いします。
Navi ということで、またまた新島章夫さんに来ていただいて、今までの聞き足りないお話があって今日は本当にありがとうございます。うちわ祭りは終わってしまったんですけども、「終わりは次の始まり」ですよね。ということで、お話を中心に、お話できたらというふうに思っています。新島さん、まず今年のうちわ祭りで、私は新島さん体調が悪くてという話を聞きました。すごい心配しました。
新島 いやいや実は本当に体調悪かったんですけど、いろんなことがありまして、それで私ちょっと熱が出ましたけど、休ましてもらって、夕方から全部出たんですけど、とにかく暑いのと、それからやっぱり同じ時期は、いつも提灯書いたり、いろいろ仕事が多かったりするので、どうしても疲れが多いんですよね。昔は全然平気だったんですけど、1週間ぐらい寝ずにお祭りに入ったことあります。でも今はそうはいきません。もう歳が歳ですから。今年は本当に終わってからちょっときつかったんで、これからまたこの暑い夏をどう乗り切っていくかってことを考えていかなくちゃ駄目だなと思ってます。
Navi そうでしたか、先ほどちょっとお話を聞いたらこういうことを初めてだと。
新島 そうですね。私は67年目なんですよ。今年ね。11歳から始めて67年目。お祭りを途中で休んだ午前中あるいは午後休むってことは今まで一度もなかったですよ。全く朝から晩までやらないと気が済まなかった。ところが今回はみんなに申し訳ないですけど、ちょっと午前中だけ休ませてもらったなんですよ。2日午前中熱が少しあったからやむを得亡いと言えばやむを得ないですが、夕方になったら少し熱が下がったんで、「それじゃ出ていこう」ことで普通にやってきました。それがあとあと尾を引いたと思うんですけど
Navi 新島さん大事にしてください。暑いこともそうだし、準備とかいろんなことがあって。皆さん夏をどうやって乗り切るお祭りをどうやって乗り切るかっていうのをやってる中で、「こういうことは初めて」っていうのだから、今年は大変な年だったんですね。
新島 そうですね。もう本当悔しいですね。とにかく休むってことなかったです。何とかお祭りが無事終わりまして、今年のお祭り自体がちょっと変則的なお祭りですから、年番町さんがいろいろ考えながらやってもらってるんですけど、変則的な道路の閉鎖時間帯とか。それから巡行祭とか日程の違いとか。それがありまして。夕食時間がずれたり、それから回らなくていい時間帯に回らなくちゃならなかったりして。そういうことが起きてますから、大変無理を言ってたんですよね。でも三日間無事に熱中症もその割にはうちの町内では少なかったんですけど、そういうことで無事終わりましたんでまあまあのお祭りだったんじゃないかなと思います。これ来年からもう少しまた考えていかなくちゃ駄目だと思うんですけど。変則にされつよ各町、自分の町内回りがあり、配慮してもらわないと回れなくなります。まあ暑い中なんですけど、何とかう無事に終わったんであれば、ほっとしてます。
Navi もう新島さんを象徴する言葉が、「悔しい」ですね。
新島 悔しいっすね。
Navi 自分なんかもう本当に最近やっとそういう3日間とか、朝から夜までっていうのを経験して、知らない人が初めて参加するとこれを今までずっとやり続けてきたっていうこと自体がすごいなと。
新島 そうですね。67年間、今、現役でやってる人は他にいないと思うんですよ
Navi いよいよそういうふうになってきましたね。伝説の新島さん。
新島 11歳までは、3つか4つぐらいから意識ができるようになってからお祭りの綱を引きに行きます。これも欠かさず3日間出て、その頃ちょっと具合が悪かったときもあったんですけど、「具合が悪い」っていうとうちから出されませんので、しらばっくれていきまして、夜まで帰ってきませんでした。ですから67年というよりも、それも入ると大変な長い期間お祭りやっているわけです。
Navi そうですね。調子が悪いって 言ったらみんな心配するじゃないですか。大体だから私も新島さんに今年はね、こういうふうに番組出ていただいたり、いろんなお話を聞いたりした後で新島さんにお会いできると思ったら昼間しか銀座のところに近づけなかったのでお会いできなくて「あれ、新島さんは何か別のところにいるのかな」って思ってですよ。直後に、「今年実は調子が悪かった」って聞いたよと思って。私は大事に至らなくてよかったなって思います「悔しい」っておっしゃいましたけど。
新島 そうですね。だって主要なところは全部出てますから。
Navi そうですけど大事にしてください。燃え尽きないようにぜひ長く、無理なさらないでって言ってもきっと、無理なさっちゃうんですけどね。
新島 だから今年そういう状況でちょっときついコースだったんですけど、来年筑波町が年番になりまして、次の年が銀座です。筑波町と銀座でよくよくこれから相談していって、そしてまたちょっと以前のような祭の形態に戻したいと思ってると思うんです。これからですけど。「石原から銀座まで」というお祭りをやってもらいたいなと。そう思います。
Navi あとはね体調をくずされないように。新島さんが無事にやれるっていうのもありますよね。
新島 あとは暑い暑いって言ったら時間帯の変更だとかね。巡行祭は夕方じゃなくて夕飯を食べる時間、時間もなくて皆さん外で何か夕飯食べたらしいんですよ。みんなね。おにぎりとかお弁当とかでそういう状態じゃなくてちゃんと夕飯が食べられるような形で。ですから午前中の巡行をやるってことも一つは考えています。
Navi なるほど。
新島 京都なんか9時から出発しますかね。9時から出たってお昼までに終わっちゃいますから、そういう形にしてそして午後の暑いとこちょっと休むと。それから夕方出てくる。そういう形もいいんじゃないかなと私は思います。
Navi 良かったです。なんか「スポーツの試合は甲子園なんかだってお昼はなくて、お祭りは暑くてもやるんですか」っていう全然関係ない人から言われて、そう言われてみればそうだと思います。祭り関係者の皆さん暑い中でも、暑さを感じないんだとか、すごいですからね。
新島 私はやっぱり今まで通りの昼の巡行祭が一番いいと思いますよ。巡行祭っていうのは各町の山車のお披露目的なんですよ。ですから昼間の明るいときに前から横から後ろから全部見られます。それから一つ一つのお囃子が聞こえるわけですね。「曳っ合せ叩き合い」のときなんかだとガチャガチャしてるから、どういうお囃子やっているかわかりません。でも、巡行祭で1台ずつ行くと、それが一つずつ綺麗な音色が聞こえてくるわけですね。だからそういう点では山車を見せること、幕を見せること、彫刻が見えること、それからお囃子が聞けること、巡行祭っていうのは本当は昼間が一番いいんです。
Navi 本来のその巡行祭っていうのは1台ずつをじっくり見ていただくということで
新島 お披露目ですね。
Navi また、いろんなアイディアが出るかもしれないということですね。わかりました。祭りの進化があるかもしれないんですけれども、さて、今年の祭りを今振り返っていただく新島さんにとっては、今年は本当につらいというか悔しいうちわ祭りになってしまったとは思うんですけれども、無事に終わったということで良かったかなと思っています。さてここで曲に行きたいと思います。では直実節いってみますかね。
新島 そうですね。このあと堀口熊五郎の話がでると思いますけど、熊五郎が先頭に立って、直実の銅像を作りました。
Navi そうなんですか。
新島 そうです。ですから直実節をどうしてもかけてあげたいと思います。
Navi わかりました。では、直実節聞いてみたいと思います。
【曲 つくば兄弟 直実節】
Navi 時刻は12時13分を回りました。87.6MHz FM熊谷 梅林堂提供 やわらか熊谷僕らがつなぐ物語 「第46回関東一の祇園熊谷うちわ祭3」ということで今日はですね、お祭りといえばこの人 熊谷山車屋台祭研究会会長の新島章夫さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。新島さん、やっぱり直実節はいいですね。
新島 そうですね。
Navi もう本当私なんか、これは染み付いてます。先ほどちょっとあったんですけど、
新島 昔はね、お祭り広場で終わったときに直実節をかけたんですよね。
Navi かけました。
新島 ですから本当は今でもかけて、やっぱり熊谷の代表的な曲ですから、直実節、子供たちをみんな知ってますから。あそこでかければ子供たちだって歌えるんです一緒に。ですからぜひ、本当はそういうふうに戻してもらいたいですよ
Navi 私も気がついてしばらくその最終日に行ってなくて行ったら、「あれ?何でかかってないんだろう」と思って、あれがかかっている最中に山車屋台がぐるっと回るじゃないですか。
新島 そうです
Navi あれの風景が素敵ですよね。
新島 直実節がかかると1台ずつ離れていくんですよ。
Navi お囃子のたたき合いと直実節、そしてぐるっと回って戻っていくあの風景は目に焼き付いてるし、体に染み付いてますけど
新島 いや本当はできればね、あそこで直実節かければね、来賓の方たちもこれは「熊谷の歌か、直実さんか」ってことになりますよね。
Navi そうですね。子供たちだって、運動会で踊ってるのでそこでかかれば、
新島 一緒にね、歌えるし
Navi そうなんですよ。私もあの直実節をあそこでもう1回聞きたいなって思います。
新島 そうしてもらいたいですね。
Navi ということでいよいよ、今日のメインの「お祭りや熊五郎さん」っていうお話にいくのですけれども。まず一つ私がお祭り熊五郎さんのことを知ったのは、新島さんからお話を聞いたのもあるんですけど、最近ちょっといろいろ調べ物をしたら、年番の札ってありますよね。その裏に堀口熊五郎っていう名前があって、お祭りや熊五郎さんって年番の札の後ろに名前が書いてある方なんだと知りました。
新島 そうなんです。年番の札は内側の小さい札が昭和42年にできたんですよ。その後にそれじゃ小さいと持った形が小さいという。外側に額をつけたんです。
Navi そう言われてみれば、何か大きくなりました。
新島 そうですよ。額をつけてもう少し立派にしなくちゃしょうがない。それで、「おめえ そのデザインしろ」っていうんで、本当はその柄が、今は青海波が、実はそこに上に縁回りが紗綾形、正しくは上に「波に龍」下に「牡丹に唐獅子」を描いたんですけど、でもそれは小さくてちょっと彫るのが大変だっていうことで、それでそういうふうな今の様になったんですけど。そこの裏に昭和61年、天皇陛下のご在位60周年で記念ってことで、堀口熊五郎もその一番下には岡野と私の名前があります。
Navi 今聞いたんですけど、新島さんの名前が年番札に入ってるんですね。やはり伝説の方ですね。
新島 その前の小さいのは堀口熊五郎と一緒にいつもいた清水康雄っていうお茶屋のおじさんっていう人がいたんですけど、この人が考え出して、そしてその札を持って。歌舞伎調で年番送りって毎年ずっとやってたんですけど、あの熊谷ってちょっと変なとこありまして、「あいつだけがやっててなんだ」ってことになるわけですよ。彼がいなくなったらひどいですよね!「誰がやるんだ」って、それで年番町の大総代がやることになったんです。この清水さんって歌舞伎が大好きでした。歌舞伎の見栄を切ってそして、あの昔は歌舞伎調で清水さんが全部お話したんですよ。
Navi 私もだから今年改めてよく見たら、がしっと決めているのがわかりました。
新島 年番札、今は額がついててすごい大きいんですよ、
Navi 決めてますよね。形を
新島 その考えをしたのが清水さんっていう人で、この人はやっぱりお祭りに熱心だったし、もう何を喋らしてもうまいですし、典儀司役を持ってました。堀口熊五郎といつも一緒にいろんなお祭りのことをやってたんです、ハワイのこととか、東京銀座祭とか、それから万博だとかそういうのにはみんなこの2人で仕掛けたんです。
Navi いろんなところに熊谷のうちわ祭りがでていくというそうです。それを仕掛けたのが
新島 そうです。この2人
Navi そして今日は特に「お祭りや熊五郎さん。堀口熊五郎さん」伝説の方
新島 そうですね。堀口熊五郎といいまして明治29年生まれなんですよ。亡くなるのは平成8年なんですけど、私がお囃子をやりだして、熊谷でお囃子に関わって初めてなんですけど、その11歳さんのときに、既に堀口さん62歳なんですよ。私は堀口熊五郎さんと話がしたかったんです。とても話ができる段階じゃない。
Navi そうですね。51歳差で
新島 私の高校生の友達が、堀口さんの2件手前で床屋やってたんですよ。そこへ堀口さんが来るってことで、その友達に、「堀口さんが来たら銀座に新島っていうのがいるんだけど、話しといてほしい」いって
Navi ちょっと待ってください。小学校5年生ぐらいの子がですよ。62歳のこの伝説の方との接点を持とうとしたんですね。最初はそういうところからスタートしたんですか
新島 高校生ぐらいになって、その同級生が。床屋でそこへ堀口さん来るしてるんですよ。来てるっていうから、「どうしても話してくれ、銀座に新島っていうのがいるからって。いろいろ話してもらったけどまだ全然話もできないし、それで私が祇園会の副会長になるのが29歳ですから、この頃副会長になってやっと全体的なところに出ていくことになりますからはい。そこで初めて堀口熊五郎と行き会うことになるんですよ。
Navi 80歳ぐらいですかね
新島 そのときは80歳ですね。
Navi はい。計算しました。そうです。29+51で80歳の方って
新島 80歳からそれから、もう本当にすごく仲良くしました。えばってたおじいさんですけど、まあ何でも言うこと聞いて、100歳まで20年間、私はお付き合いしました。
Navi そうですか。なるほど。
新島 この堀口熊五郎さんっていうのは熊谷のこと。熊五郎の熊が熊谷のクマがついてますから、だから、熊谷のことを「大した観光がないし、有名なものがない。これじゃしょうがない」と熊谷のことになったら何でもいいからってことでいろいろ宣伝したり行動したりしたんですね。昔、熊高が昭和24年甲子園出ました。そのときに、熊五郎さんは、市会議員ですよ。それで甲子園に行きます。そうすると甲子園の放送で、「くまたにこうこう」熊谷高校って放送ですよ。それで頭にきちゃっておじいさん放送室まで行って、「お前何言ってんだって。熊谷次郎直実知らないんか!こんな有名なのがいるじゃないか。何が「くまたに」だってみたいな、怒ってきたんだ。」それ話なんですよ。私はだって24年ですから、私はまだ3つでしかない。
Navi 熊谷をこよなく愛する方ですね
新島 そういうこともあるし、それから、熊谷から初めて宝塚に出た文月玲。この人が熊谷から出たときに、「あんたは偉い」ってね、わざわざ宝塚まで飛んでいくんですよ。熊谷が宣伝できて、「お前宝塚行ったんで偉いから」ってお褒めの言葉をやってくんですよ。もう一つ熊谷の石原の若松若太夫。かなり前にこの放送でやりました。その若松若太夫が新聞に出たときに、すぐすっとんでいって、「お前、熊谷のせがれだから。すぐに春に講演するから熊谷会館で大々的に講演するから」って言って講演しました。そういうことが大好きなんですね。
Navi なるほど
新島 私と一緒にお祭りをハワイで「まつりinハワイ」ていうのがありまして、これも清水やすおさんと堀口熊五郎さん、そして私達で行ったんですけど、ハワイに山車を持っていくことはできないんで、山車の形を作るために向こうで材木を用意してもらって、参加者の中に大工さんが3人居てその材木を皆さん見てる前でそれを刻んで組み立てて、そして山車の形にして、破風板だけはこっちから作ってくっつけて、そしてトラックの上に乗せて。カラカウア大通りを巡行したんです。
Navi ハワイで?お囃子を?
新島 そうです。
Navi それ何年ぐらいですか。
新島 昭和55年1980年
Navi 私はこの頃はもう生まれて高校生ぐらいだったのかな。そういうことがあったんですか。
新島 それからその後亡くなるちょっと2年前ですね。京都の平安遷都で銀座の山車が行ったときに、おじいさんも行きましたよ。一番先頭でパレードしたんですけども、京都の八坂神社の正面から出てって四条通から、河原町それから御池通り、そこを通っているんです。それを先頭で車いす「亀さん号」っていって、スイッチで亀さん号だけどウサギさんというスイッチもあったちょっと早いんですよ。うさぎさんにして、「お爺さんそれじゃあみんなおいついて行けないよ。」歩いて一緒に周りが行くんですから2人ぐらいが担当して、そして、亀さん号でそして前には。「曳き綱を引いて90年 生涯奉仕」っていう札を下げて、京都へ行った時に調べたら「晩年奉仕お祭屋熊五郎堀口熊五郎98才」と書いてありました。
Navi 98歳ですよね。
新島 そうです。そのときに行ったのが、そうです。98歳ですよ
Navi あれですね、あの伝説の銀座の山車を持っていったときに、熊五郎さんも行ったということですか
新島 一緒に行きます。はい。
Navi それは熊五郎さんとしても、とても感無量じゃないですか。
新島 2年後に亡くなりました。冥途の土産ですね。「生涯奉仕」書いて、祭りに携わり95年でそういう札を下げて、堂々と車いすで、本当にこの人はね、それが様になるんですよ。支度もかっこいいですよ。半纏着ててあの花博のときは花の展覧会と描いたちゃんこみたいに作って着ました。そういうふうに祭のときはちょっとしゃれた着物の首抜きっていうかな。ここんとこに自分ちの家紋が入るやつ。それを着て、そしてそういうかっこいいっすよ。だからそれで、結構いろいろってわがままいって。それで強引なんですよ。
Navi 強引?
新島 でもさっきの若松のことなんかも、来年の春のことを、暮れの忙しい28日に「みんな集まれ」っつって。強引に集めて、「だって暮れに来年の春のこと今日じゃなくていいんじゃない?」っていう話をしたんですけど。そういうことがあって、とにかく結構いろいろ「これやれ、あれやれ」って言うんですよ。私もね、「そんなにおじいさんの使い子をやってるわけじゃね」かな言ったことはですよ。
Navi だんだん言えるようなってきたんですか。
新島 ところがあの人が笑ったときの顔を見ると「ああ、この人のためには何でもしちゃうんだ」と思うほどね、子供はもう嬉しくて、いたずらをしていて嬉しくて、そういう顔をするんですよ。だって小さいときからもうおじいさんですからね。私の一つ下の一緒にやってた祇園会の副会長がいたんだけど、西村っていうのは「堀口さんは生まれたときからおじいさんで、未だにおじいさんなんだよ。」だから本当にもう知ってる時は60過ぎですから。だからもう当時62は大変なおじさん。それがずっと変わらずにいるわけですから。その笑顔を見ると、「このじいさん うるさいけど、しょうがねえ 言うこと聞いてやるか」って思っちゃうんですよね。俺はね。
Navi そうですか。
新島 本当にその笑顔がなんともいい顔するんですよ。よしこれじゃ、しょうがねえ「年寄りだから」って本人が言うから。「おめえ俺が年寄りでな、年寄りが若いやつのためにやるんだから年寄りいうことは聞くもんだ」とそうに言うんですよ。
Navi 様になりますね。そのいい方が
新島 うん。俺一回だけいうことを聞かないことがあったんですけど。でもそれでも「おめえなんとか言うことを聞いてくんない」っていうんで、そういうことがあったんですよ。でもね、死ぬまで、明治29年に生まれて、満100歳、平成8年のお祭りの前の日、7月19日に入院します。そして20日21、22となって23日の朝亡くなるんですよ。お祭りの前に入院して、ところが7月21日には正気だったんですよ。22日はちょっとわかんなくなって、21日の巡行祭やってたときに、おかみさんに「おめえちょっと新島すぐ呼べ」って。そしたらおかみさんが「今ね、お祭り巡行祭やってる日だよって、とっても来られないでしょ」って言ったらしいんですよ。何が言いたかったかちょっとわかんないけど、私はちょっとそれが残念なんだけどなにか言いたかったと思うんですよ。ですからお祭り中だからたぶん言われても行けなかったと思うんですけど次の日はもう意識がなくなっちゃって、その明け方なくなったんですけど、亡くなって23日ですから、終わって私は片付けしだしたら、電話がかかってきて「亡くなったから」そしてその入院してる先に行って遺体を私は自分の車で運んでくんですよ。うち近くまで、だから最後の最後まで堀口さんと関わって、それも葬儀の担当を全部さしてもらって、本当にね、堀口さんって自分で「お祭りの中興の祖」って言ってんですよ。それで、お墓の碑の後ろに全部そういうのが書いてあります。昔は魚屋で、骨董屋やって、不動産やって そういうのがあって、そしてお祭りの中興の祖だと。というのは昭和12年あたりから、熊谷のお祭りやってないですよ。これ16年だと思ったけど。そして22年までしなかったんですよね。その間「何とか、これじゃしょうがねなと、おまつりしなきゃしょうがない。神輿は焼けちゃってるし」
Navi 戦争で中断してたってことですよね。
新島 それで神輿の部材をどこからかあるうちからいただいてるんですけど、それで神輿を作って、そして何とかお祭りしなくちゃいけない。そして22年から本格的な祭りを始めると、ですから自分でもずっとそのまま戦後ですから、多分もしかしたらおじいさんみたいな人がいないとそのまんま幾年も続けてやんなかったかもしれないですよね
Navi 堀口熊五郎さんがいなかったらできなかったかもしれないですね。
新島 「何でかんでしなくちゃいけない」と
Navi 「祭りをやるんだと」
新島 そう。「熊谷はお祭りがなくちゃ。あとは見せるのがない」っていつも言っていましたね。だからそういう形で、多分おじいさんが頑張ったから今の祭りに繋がってきたと私は思うんですよ。
Navi この「お祭りや」っていう名前は誰、周りの人が言ってたんですか、それとも
新島 自分で「俺はお祭り屋だ」とお祭りや熊五郎ってつけて、私もちょっと「お祭りや2世」とかって言われるんですけど
Navi まさに「お祭りやさん」だと思いますけど。
新島 だから八坂神社行きますと、一番左の入口の一番左の大きな玉垣に「お祭りや熊五郎」って入っているんですよ。
Navi 文字が彫ってありますよ。それはちょっと私も見させていただいたんですけども
新島 すごいですよね。
Navi 本当にこの方は、やっぱり「中興の祖」っていうのはいわゆる1回駄目になっちゃった祭り、ちょっとしぼんじゃった祭りをちゃんと興して、そして現在のこの繁栄というか、うちわ祭り、現在の熊谷の祭りは派手に盛り上がって皆さんに注目を浴びてるっていうのは、そのスタートのところから
新島 神輿は焼けちゃってますけど。鎌倉町の屋台と神輿彫刻の四神旗なんかみんな焼けちゃってましたから、その神輿を作ったってことは多分すごいことだと思います。そのいろんな部材を持ってた人がいたんですよ。それを使って作ってもらうわけです。それはもう堀口熊五郎以外誰もそういうことを考える人はいないですよね。
Navi なるほど。やはり「何とかしよう」っていう気持ち、それからいろんな人を呼んできたり、いろんな人にお願いしたりするというか ボスというかなんていうか求心力ですかね。
新島 私は堀口熊五郎からいろんなものをいただいて、99歳の白寿の時、私も一緒に役員やってたんですけど、「お前はお祭り一生懸命やってるから。家宝としてやるから」実際のお神輿ですよ。綺麗な幼稚園の子供が担ぐぐらい高さが鳳凰まで80センチぐらい それから下が台座っていうのが、26センチで屋根が30センチぐらい。
Navi かわいいコンパクトな感じですね。
新島 でもそれはすごい値段ですよ。言っていいのかどうかわかんないけど、当時250万くらしした。それを本当に神社の神輿とほとんど変わりなく全く同じように作って小さいだけですか。それでお祭り一生懸命やってるからって、「家宝にしろ、せがれにもよく言っとけ」と
Navi 家宝ですからね。ずっと続いていくってことですよね。
新島 それでもう一つおじいさんがすごいのは、私のところにあるんですけど、羽子板なんですよ。熊谷直実と敦盛が下にいて、羽子板市でお店にでっかいのありますね。看板にする1m10センチくらいのやつね。これは岩槻人形歴史館に、そこに置いてあったんですよ。そこへ行ったときに、おじいさんが強引ですから「直実と敦盛はここにあってもしょうがねえ。これは熊谷にあるべきだ」といってそれで「白寿のお祝いに何とかしろ」っていうんでいただいてるんですよ。いただいてっていうか買うんですけど。それも私のところにあります。
Navi 熊谷に持ってきたと。それを岩槻から?すごいですね。
新島 あとは自分が着た絹の半纏なんですけど。それとか巾着ですね。巾着も根付が、象嵌が直実の扇子をこうやってるとこなんですよ。それから煙草入れとか。そういうの「みんなをおめえが持っていけ」と、全部私のところにあります。
Navi すごいですね。何とか記念館ができそうなそうですよね。お祭り記念館とか。お祭り会館みたいのがあったら、
新島 私の祭りの道具だけでもめちゃくちゃありますからね。
Navi そうですよ、家いっぱいあるみたいなことも聞いてます。まさに祭り会館みたいのができたらいいと思いますよ。本当に熊五郎さんのお話やっぱり貴重なお話でね。ありがたかった。
新島。この堀口さんは本当に熊谷のことを愛してましたね。例えば佐原で特別な山車引きが合ったんですよ。そんときに佐原でこういうのがあるから
Navi 佐原ですね。佐原っていうとこありますよね
新島 千葉の佐原ですね。山車は全部揃ったんですよ。あそこが春と秋は別なんですけど、それも一緒に全部だして、それでその記念式典があったときに、「バス仕立てろ」って。おじいさんが全部出してくれた。それで私の関係者みんな連れて見に行ったんです。また、千社札の会がありまして。そこにおじいさん入ってたんすよ。それでその京都の八坂神社、納額堂ってとこがあってそこに額が二つ上がってますけど、堀口熊五郎の名前が入ってます。そのあと山寺いったことがあるんですよ。
Navi 山寺?
新島 東北の山形県の山寺です。そこでおじいさんは歳取ったから、もう車の中で待ってたんだけど。そこの売店の女将さんが、「せっかくだから、根本中堂で行ってくれば、階段上がればすぐだから」って言われて、上がってくんですよ。2段目上がったら、そこで落ちちゃうんですよ。踊り場のとこで止まってたんですよ。帰ってきた頃「あれ なんか同じ半纏着てる人がいましたよ。階段から落ちたたらしいです」って言われて。びっくりしてって行ったら、落ちた下に小砂利があってその小砂利が頭の中に刺さってたんですよ。血がにじんでいて、頭打ってますから。「これじゃ大変だ」って、マイクロバスの椅子を全部外して寝るように作って、そこで寝かしてそのまま帰ってきたんすよ。それで、とりあえず近場の病院で見てもらって、治療したんですけど、熊谷市に帰ってきて関東脳外科すぐつれていったんです。そしたら、「いやこの人すげえ」って、もう傷は全然平気だった。治ってる。砂利を埋め込んで傷は治って、心電図も別に異常ないと。だけどね。びっくりしましたよ。そのときが95歳で階段から落ちてんですから。8段くらい落っこちて。
Navi 不死身の体です。正直伝説だらけですね。
新島 だからすごいあの体もデカかったですかね。私よりずっとでかかった。
Navi 堀口熊五郎さんを語ると言ったらやっぱり新島章夫さんしかないかなというところで。まだまだっていうところだと思うんですけど、ここで曲に行きたいと思います。今度の曲は霧島昇さんの誰が故郷を思わざるをお届けします。
【曲 霧島昇 誰か故郷を思わざる】
Navi 時刻は12時45分を回りました。87.6MHz FMクマガヤ、やわから熊谷僕らがつなぐ物語 関東一の祇園熊谷うちわ祭3をお届けしています。さて新島さん、本当に堀口熊五郎さんのお話をしていただいたんですけれども。今私は、改めて「お祭りや章夫さん」と呼びたいくらいなんですけどもね。新島さんにとってのうちわ祭りとか、今までの話も含めてですけどどうですかね。
新島 そうですね。私の小さい時から比べると遥かにお祭りが変わってます。67年間の間でいろんなものが変わってますよね。まず一番すごいっていうのは、昔はコースも何もなかったんですよ。今日はあっちいく、今日はこっちいく思いついたところへいく、そういう感じだったんすよ。
Navi そうなんですか。
新島 ですから「せっかくここまで来たんじゃ向こうまで行っちゃべ」そういう感じだとか。そういうことが多かったですね。それで時間も別に何時に終わりにするとかって決まりもなかったんで、そういう形が自由だったんですよ。ですからどっかへ行ったら「どこかの山車が来たからそこへぶつけをしよう」そういう形をとって、あとは巡行祭とか何かはちゃんとありましたよ。そのときの巡行祭っていうのは、今でもその頃が一番いいと思うんですけど、年番町の町内に全部が集まるんですよ。そこから出発。ですから銀座のときは銀座の地区へ全部が来てもらって、そしてそこから出発して街中を1巡するとそういう形をやってたんすよ。それがいつからか、鎌倉町と仲町のところから出てるようになったんです。そういうこととか、それから祭り自体がすごく派手になってるし、それから衣装も昔から比べると遥かに変わってますし、今のかっこいい皆さん支度してますけど半纏とか、ももしきはいて、そして頭に何かをつけてきてですけど、いろいろしてますけど、昔はとにかくカシラも今みたいな股引とか、腹掛とかしてないで。ダボシャツかあるいは丸首の普通のシャツ、そして7分ぐらいの半ズボンですね。それ履いてやってたんです。それで私達お囃子は裸でおなかにさらし巻いて。そして半纏1枚で、下は昔あったトレパンってわかります?
Navi はい知ってます。
新島 そのトレパンが下で叩いてたんです。それがいつからか、支度が変わって私はまだみんな何もしてないときにももしきを作ってもらって、股引を作る家をお母さんが知ってる人がいましてね。作ってもらって、お囃子会で股引はいたのは初めてじゃないかなと思うんだけどでも、そしてちゃんと羽織って。そういうふうに変わってきてそれから山車のきれいさも、最近は特にどっかの町内で必ず綺麗に塗り直ししたとか、幕を新しくしたとか。それから何だろう、修理をしたとか、そういう形のものをやってますよね。昔はもう本当にね、山車小屋から山車をだしてホースで水をジャージャーかけて簡単に掃除してそんなもんですよ。山車を大事にするってことなんかそんな重きを置いてなかったです。でも今はすごいっすよ。そういう美的なものを感じるということが多くなってきたし、そして文化財的であるってことで大事にするようになった。そういうことでは、非常にみんな頭が進んできて、そして大切にするようになりましたね。そういうところはだいぶ違いますね。
【エンドテーマ流れる】
これから新しく関わってくる子たちもいますが。それにはやっぱり何が一番大切かっていうとお祭りの内容をちゃんと知ることですよね。内容知らないでお祭りやったんじゃ本当の祭りがただのお祭り騒ぎ的になっちゃうんすよ。でもやっぱり同じ意識をちゃんと知ってたらすごくこれはこういうことなんだといやこれ私達やっていくと大切なことなんだと、そういうことがわかると思うんですよ。ですから私はいろいろうちの町内では子供たちにちゃんとそのお話を聞かせてます。そういう歴史をよく知って、そしてお祭りの内容を知って、そしてお祭りに関わってもらうと。それから神事とつけ祭っていうのあります。この神事は変えてもらっちゃ駄目ですよ。でもつけ祭りっていうのは後でつけて、ご存知の名前の通りつけた祭りですから
Navi 山車とか屋台が回ることをつけ祭りっていうことですよね
新島 ですから本祭りのお神輿さんが飾られて、そして式事をやってそういうのを、それを神様に賑やかしを見せてやることが神賑行事っていうんですけど、それが付け祭りですよ。このつけ祭りはどう変わってもいいと思うんですけど、神事のところが、最近はちょっと変わってきつつあるから「これはまずいな」とここだけはどうしても守ってもらいたいとこれは年番町がちゃんと上の人がちゃんと祭りのことを知って、そしてやってもらうことが大切だと思うんですよ。つけ祭りは山車だとか、あるいはその周りの付属のものだとかっていうのについてそこはどうやっても、例えば万灯を作ってもそれは万灯を持ってるとこもありますけど、そういうものもありますし、つけ祭りは自由に変えていいと思いますよ。お囃子にしても、それから支度にしても、それはもういいと思いますよ。神事は、支度なんか全く変わってないですかね。昔からね。ただ半纏なんかはね、4年に一度とか年番が来るから8年に一度取り替えるんだとかってそういうこともありますから、それから浴衣もやっぱり変えたりしてますよ それはそれでいいってことですよ。そしてつけ祭りの面白味っていうのをやっぱりみんなで作り出して、うちは、特別お囃子なんかは違いますけど、それはそれなりの意味があってやってるんですけど、ですからそういう形で皆さんがお互いに競って、よりよい祭りを作り上げることが大切です。とにかく神事とつけ祭りっていうのは、別であるという。
Navi 大事なお話をいただきました。まだまだお話伺いたいんで、また来てくださいね。
新島 はい。
Navi 今日は本当にお祭りといえばこの人、新島章夫さんに来ていただきました。今日はありがとうございました。
新島 はいどうもありがとうございました。
Navi また来てください。
新島 はーい。