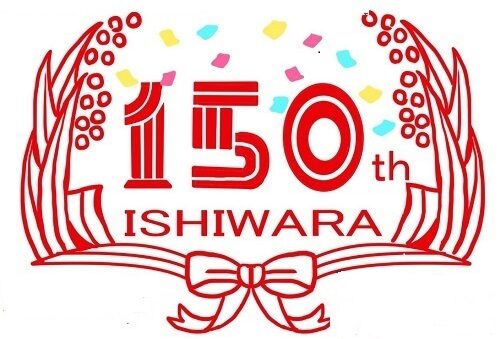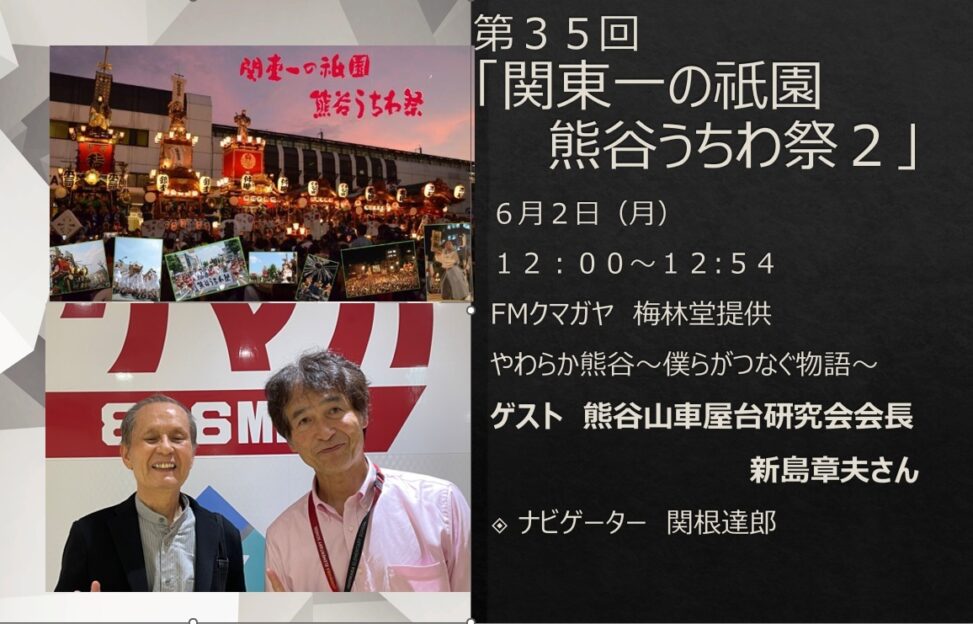6月2日(月)12:00~12:54梅林堂提供 やわらか熊谷僕らがつなぐ物語
前回放送した「関東一の祇園熊谷うちわ祭」では語り切れなかったお話を伺いします。ゲストはうちわ祭といえばこの人 熊谷山車屋台研究会会長 新島章夫さんです。うちわ祭の本の出版 銀座区の屋台から山車に変わったお話、1200年祭参加のエピソードだけでない お祭りエピソードをお聞きします。2か月をきった今年のうちわ祭 新島さんのお話で益々うちわ祭りまで待てない!どうぞお楽しみに!
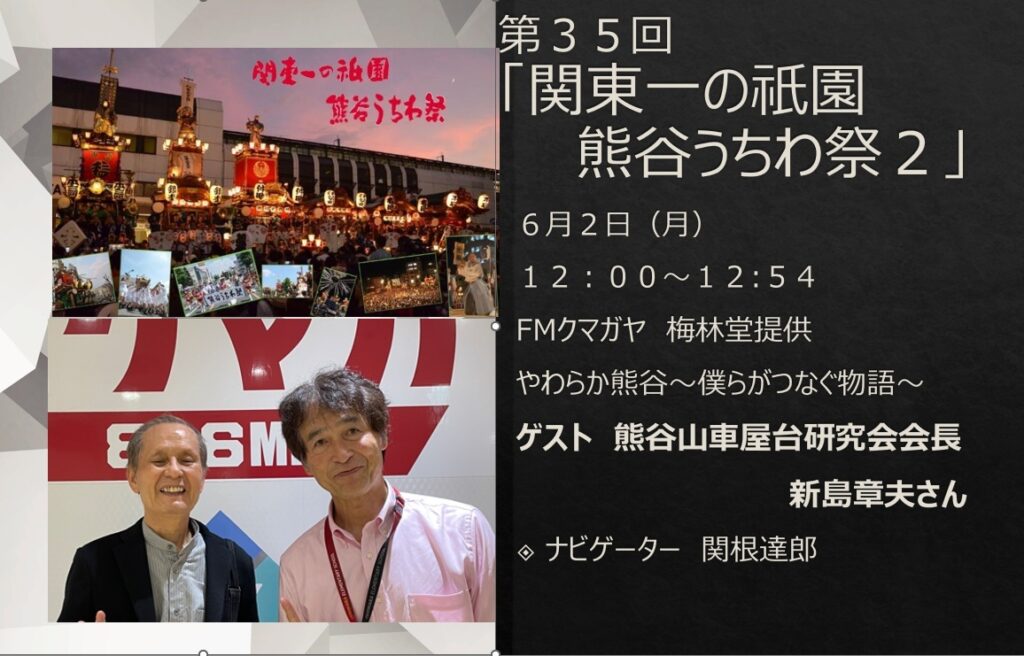
第35回 熊谷うちわ祭の歴史と伝統を語る新島章夫さんとの対談
⏰月曜日 2025.06.02 12:00 · 53mins
文字起こし
Navi 時刻は12時を回りました。AZ熊谷6階FMクマガヤYZコンサルティングスタジオから生放送でお送りします。月曜のお昼は梅林堂提供やわか熊谷~僕らがつなぐ物語~をお届けしています。さて今日は第35回関東一の祇園熊谷うちわ祭2というタイトルうちわ祭Part2ということで、前回出ていただいた時の話し足りなかった部分を続編ということになります。ゲストは熊谷山車屋台祭研究会会長でうちわ祭りといえばこの人 新島章夫さんに来ていただきました。こんにちは。
新島 こんにちは。新島ですよろしくお願いします
Navi お待ちしていました。前回新島さんにお話していただいて、本当にちょっとしかお話が聞けなくてまだまだいっぱいあるので、無理を言ってまた出ていただきました。前回は先々週だったのですけど、今日はありがとうございます。さてちょっと前回のおさらいをしたいと思うのですけれども、こないだのお話は、まずうちわ祭りの本を作られたということでした。「関東一の祇園熊谷うちわ祭」といううちわ祭の教科書と言った本を作られたという話、その本は熊谷のこと、熊谷のうちわ祭のことが詳しく書いてある本です。それがまず一つです。2つめ新島さんは今まででうちわ祭っていうのは、元々熊谷の人がお囃子を叩いてなかった時代があったのですよね
新島 そうですね。みんな各町内が岡部深谷だとか遠く本庄、中之条そういうとこからも来ていたのです。
Navi お囃子の人に叩いてもらってそれを見てというお祭りという形だったのですね
新島 そうですね。私も見ているだけで、屋台の上に「乗りたいな。乗りたいな」とずっと思ったのですよ。そしてちょうど11歳になったときに、うちの町内で初めて、地元でお囃子やろうじゃないかっていう話が出ました。
Navi はい。
新島 全部大人を集めたのですけど、私は子供で1人だけ混じって入っていました。
Navi 熊谷の人が初めて叩いた年は昭和32年ですね。
新島 そうです。
Navi 新島さんは熊谷の子供として初めて屋台でお囃子を叩いたという人だったということでもそれはびっくりしました。パイオニアですよ。それからいろいろなお話も聞いたのですけれども、あとは銀座区が屋台から山車になったというお話を聞きましたね。
新島 はい。平成6年ですね。
Navi 銀座の山車を見て、びっくりしたし、そしてその上に乗っている人形は熊谷次郎直実という
新島 そうですね。そのときいろいろお話もいただきました。
Nav でも今はもう当たり前ですね
新島 苦情が出ましたけど今は、もうみんな理解できると思います
Navi というお話を聞きました。まだまだあるのですけど.京都で1200年祭というお祭りがあって、
新島 そうですね。京都が1200年祭ちょうど平安京ができてから1200年ですね。そのときに京都はなんと言っても八坂神社が本家本元ですから、各地に広がった山車を京都によぼうという大きな計画ができたのですね。その中に熊谷が入りまして私が関わりまして、そして銀座の山車を持っていくということになります。
Navi しかもその持って行った日が、うちわ祭りの最後の日だったのですよね。
新島 そうです。
Navi 終わった後で寝ないで持っていった。
新島 そうです。22日のお祭り広場が終わって、そして23日の0時から、還御祭があります。そのとき私はちょうど祇園会の会長やっていましたので、これを欠かすわけにいかないし山車の方は22日の10時過ぎにはもう帰ってきまして、すぐトレ一ラーに乗せて運ぶようにして、私達は1時半になって、そしてバスに乗っていきました。実は23日のお昼までに京都八坂神社四条通に全国各地から来た14基の山車全部並んでなくちゃいけなかったのですよ。ギリギリお昼までに何とか間に合うようにして、そして何とかくみ上げて出来たのが12時ちょっと過ぎだったのです。
Navi お祭りの3日間、暑い中でやって疲れた皆さんが決死の京都ですね。すごいドラマチックですね。それを聞いただけですごいなと思っていす。伝説です。皆さんに伝えられていと思うのですが、「私も行ったよ」っていう人いました。新島 やっぱり本拠地の京都の八坂神社の前で、実は向こうの京都の山車も八坂神社のその前まではいけないですよ。それから四条大橋を渡るってことはしてないのですよ。全国からきた山車は四条大橋を渡ったのですよ。これはすごいですよね。
Navi すごいですね。
新島 銀座の話は平成6年そのあと平成17年になると、今度は江戸開府の400年祭で、本三四が2年前に行って、そして2年後に銀座の山車が東京にいきます。そうすると、古都京都とそして現在の都の東京で、千代田区ですね。ビルの中を引き回されたことになりました。
Navi なるほどね。
新島 東京も京都もそうです。あの直実公は両方行っています。
Navi なるほど絵になりますね。やっぱり行ったか行かないかっていうのは大きいですよね
新島 お囃子だけいくっていうのは結構あるのですよ。でも確かに山車もそっくり行くっていうのはこれなかなか難しいのですよ。こんなこと言っていいかどうかわかりませんけど、京都に運ぶにも運び代だけでも210万とかかりますね。
Navi そうでしたか。大きなイベントというか、すごいことですよね。
新島 そうですね。だいぶ若いとき50歳、そのときだから勢いもあったし、もう何をやっても平気だったのですよ
Navi 「目標のためにはやる」ということですよね。そんな何回もあることじゃなくてしかもね、ここだっていうチャンスが巡ってきたときにどうするかですもんね
新島 そうですね。京都行ったときって平成6年だし、平成6年は私の町内が年番町であって、屋台から山車移った年で、新しい山車を京都に運ぶ、すごい行事が重なっているのですけど、山車を作るっていうのは、ここのところ荒川、伊勢町が山車になりましたが、これ本来ですと50年100年に1回あるかないか自分が生きていてめぐりあうことはないと思います。行事っていうか、山車の新調をするというそれはなかなか巡り会わないのですよ。それを巡り合えたってことは、私はもう「神様がご褒美」としてもらえたのじゃないかなと思っています。
Navi なるほど
新島 年番と京都と山車と、もう私にとって本当に神様からのご褒美だと思っています。
Navi この熱い思いはでいろんな巡り合わせが重なると思います。偶然もあるかもしれないけどやっぱり何もしないで重なることはないですから
新島 そうですね、やっぱり京都とか東京もそうですけど、私が関わりないとそれは難しかったですよ。東京の天下祭りで私は千代田区の実行委員やっていたのです。それで選ばれて実行委員をやりました。
Navi やっぱり何か伏線があってのことだと思います。やっぱり何かチャンスを呼び込んだりすることは一生懸命に続けていくこととかすごく大事なことですね。
新島 お囃子だけだったら滋賀県行ったり千葉県行ったり、いろんなとこ行っています。それをやっぱりお祭りに関わりのあるちょっと上の人たちから連絡がきて、「来てくれないか」とか「やってくれないか」っていう話があります。
Navi そもそも私最近気づいたのですが、お祭りっていうのはやっぱり人と人を繋ぐものなのかなって思うのですよね
新島 そうですね。やっぱりお祭りは、私60何年やっていますけど、その中で年長者から幼児までお付き合いしている。お祭りは年寄りから若い人たちまでが関わっていますので、そこで一つの繋がりがすごく広くなりますよね。
Navi そうですよね。そして絆は強くなります。だってみんなで困難を乗り越えることってあるじゃないですか。
新島 そうですね。
Navi 祭り中もいろんな何かあったりするし一つ作り上げるのにはやっぱり皆さんの結集がないと駄目ですね
新島 各町はお祭りをやっていますが、やっぱり自分のところを一番にしたい。何とか良くしたい、かっこ良く見せたいっていうことで、やっぱり団結しますね。町内でまとまってものごとができるってことはやっぱりお祭りはすごいことだ
Navi そうだと思います。私も去年から参加してこれだけの人が真剣に取り組む。大人はすごい真剣じゃないですか。そこがやっぱり祭りの結束っていうか、それぞれ町内は自分たちが一番だって思う気持ちが強いですもんね
新島そうです。自町の誇りとか、権威とかそういうのが強く表したいですからね。
Navi だからそれがこの3日間に集まるということですね。この3日間なんですけど初級のお話になると思いますが、ラジオを聞いている方にもちょっとお伝えできればと思うのですけど、まず1日目、どんなことが始まるか朝からですよね。
新島 熊谷のお祭りは20、21、22日になっていますけど実質的には23日とそれから19日前の日で夜ですね。おみこしに魂を入れます。これは祭りの始まり19日の晩、昔は深夜、夜中0時にやっていたのですよ。でも今は9時頃にして、そして神様にお神輿に乗ってもらう。
Nav はい。
新島 それやっといて、そして翌日の朝6時に八坂神社、各町の総代組頭祭事さんが集まって渡御祭をします。
Navi 八坂神社っていうのは上熊谷駅の近くにある八坂神社ですか?
新島 そうです。他に皆さん集まってそこで発輿祭って神輿が出る式典をやりす。そして、そこから鎌倉の踏み切り渡ってそれで荒川をちょっと回って伊勢町にちょっとかかって全町を一回りします。そして10時半頃には、御仮屋ってお祭り広場に来ていますが、その御仮屋に御神輿が到着する。
Navi なるほど御仮屋っていうのは、ちょうどお祭り広場のところに、臨時の神社を、建てるのですよね
新島 「いくみや」って書く 本宮からから出ちゃった行宮(あんぐう)っていいます。御仮屋ともいいますけど、そこへ納めて、そして3日間は神社じゃなくて「神様が町の中に私はいますよ」って表現するわけです。そしてそこで近場の人はみんなお参りができるようになるということですね。それでお神輿は、動けない人たちのためにも、神様が来ましたよってことで回ってくれるわけじゃなるほど動けない人はうちの中で手を合わせて神輿が通るのを拝んで、そして見送ります。
Navi なるほど祭りの全体像を見る上で、だからなぜおまつり広場に行ってうちわとかももらえるのかっていうとそこに大事な御仮屋ができていてっていうことですね
新島 3日間町の中で神様がいますよっていう
Navi やっぱりうちわ祭りに行きましたら、お祭り広場に一度行って御仮屋に行くことが大事ですよね。
新島 そうですねお参りしてもらった方がいいです。そして夜1日目の夜は駅前に各町全部12台が集結して初叩き合いっていうのをします。
Navi はい、これが横にずらっと並ぶのでね。はい。これ見栄えが結構いいですよね
新島そうですね。あのように近くに寄せて横に1列に並べるっていうのはこれ3輪独特の動きですから、これ4輪の車がやっているとなかなかそういう形にするのに大変な時間かかっちゃいます。
Navi 今のちょっと解説させていただきます。熊谷の屋台や山車が3つの車輪が付いていてこまめに動ける(小回りが効く)のでと綺麗に横に並べることができるのですよね。ほかの地区は4つの車輪のことが多いです。1日目の駅前のその横に並んでいるところも結構賑やかで素晴らしいですよね
新島 そうですね、
Navi 私も本当に1日目の駅前の叩き合いも素晴らしいなっていうのを去年実感しました。1日目はそこでたたき合いをするという。そして2日目、
新島 2日目は昼間から本来ですと13時から巡航祭、各町が全部鎌倉町と仲町のところで終結しまして、そこから石原に向かって、山車屋台が迎えにいきまして石原を連れてきて、そして御仮屋で神様を参拝してそして銀座の方まで行って、そしてそこで最後の叩きあいをして、そして解散するという形です。でも今年はそうじゃなくて夕方からやります。そして範囲が狭められて石原までも銀座にもいきません。ちょっとこれ残念なのですけど。そういう形で巡行祭は本来各町のお披露目なんです。
Navi はい。そうですか。
新島 ですから昼間夜と違って昼は彫刻や、あるいは形や、それから幕とかいろんなものが本当によく見えるわけです。そういうのをお披露目するためのものが巡行祭
Navi また解説になっちゃうのですけど、17号国道をまず歩行者天国にします。そしてそこを各町が全部練り歩くというのが巡行祭という形になりますかね。そして昼じゃなくて今年は夜行うということになるそうです。
新島 夕方からですね、
Navi 昼間は歩行者天国になってるってことですよね。
新島 そうです。
Navi そうやって山車屋台はぐるぐる回っていて歩行者天国があるので人としてはですね。今回2日目お休みですからね人がたくさん出るのは2日目ということですよね
新島 そうですよね。
Naviはい。そして3日目
新島 3日目は午前中に行宮祭っていうのがあります。さっき言った御仮屋さんで、行宮祭式典を行います。そして大総代が装束をつけて、そしてこの2日間が無事に終わって、またあと1日を、これを無事に過ごしてくださいと、そして市民がみんな平和でありますようにというようなことを願うわけです。そしてそれが終わったら、今度は各町に戻って、各町をみんな回ってそして夜になったら、お祭り広場に集結します。
Navi そしていよいよフィナーレ。
新島 そしてお祭り広場で年番送りがあって、次の年番に移る形をします。そしてそれが終わったら、23日の0時にならないと、還御祭はできません。お神輿をお返しすることですから。だから0時になったら神輿が動き出す。昔はこれすごい距離があったんですよ。23日の朝6時からやってたんですよ。渡御と同じ所を回った。でもそれがもうクタクタになって皆さんね、そしてお酒も飲むし、出てこない人もいるし、神輿が運べなくなっちゃう状況が起きてくるんです。ですからまだ元気なうちに「23日の0時になったらやっちゃおうじゃない」っていうことで、今の還御祭になっています。
Navi なるほど
新島 1時間半で収めるっていうことです。
Navi わかりました。また解説に戻りますけれども22日はとにかくお祭り広場に集まっての叩き合いが一番華やかだと思うんですね。たたき合いをして、そして年番送りをして、そして各町に戻ると、それでその後これで終わりじゃなくて0時にお祭り広場に行くと、還御祭っていうのをやってるということだそうです。私も去年初めて還御祭を見させていただき、本当におっしゃってる通りでお神輿が来て、あんな夜中なのに、いろんな方々がやってるなってびっくりしました。そしてまたお神輿がまだ回るんですよ。そこから。
新島 そうですね私は祇園会の会長(このとき副会長・半纏の文字を祇園でデザインする)をやったときに、それまでの各町それぞれの袢纏だったのも神様にお還しするので白装束に白い袢纏にします。今は、各町祇園会のマークを入れた白半纏を作って、そして担いでいます。
Navi もしこの話を聞いて興味があったら、12時過ぎても、おまつり広場でお祭りが楽しめるということなのでぜひぜひ
新島 迎える若い人たちが400人ぐらい集まって担ぎますんで。
Navi そうですよね。私もそれを見ましたので、ぜひこれはね、言っていただけたらと思います。そして叩き合いが終わった後にね、屋台が戻るときってのは寂しいものなんですが、そこでまた各町、去年本石で見たら帰りは鎌倉囃子っていうのをやっていつもと違うお囃子をしながら戻っていましたが、なんか銀座区は帰るときとか叩きあいが終わった後の笛の演奏に特徴があるというのを伺ったんですけど。
新島 叩き合いの後、解散するとどうしても、あの喧騒の中から一つずつ抜けていきますから、寂しさを感じます。だから同じお囃子やっていても、聞いてる人たちにすると、すごく寂しそうに感じるんですよ。(1台ですからね。)でもうち銀座の方はそこで帰りに、昔ながらの日本の懐かしい童謡唱歌、それから流行歌とそういうものを全部含めてやってます。そして子守唄あるいは花嫁人形とかそういう曲をやりながら帰ります
Navi ということですよね。私もびっくりしちゃったんですけど、屋台とか山車っていうのは、そもそもね、舞台なんですよね。そこでお囃子っていうかその曲を演奏するっていうのが本来の姿ですよね。改めて今日聞いてしかも曲名がいろいろ出てきたんですが、この後、実はその内の一つ同様の「りんごの独り言」というのをやってるということなので、ちょっとこの曲聞いてみましょうか
新島 そうですね
Navi はいでは童謡で、「りんごの独り言」をお届けします。
【曲 童謡 りんごの独り言】
Navi 時刻は12時26分を回りました。87.6MHzFMクマガヤ 梅林堂提供やわらか熊谷~僕らがつなぐ物語~第35回「関東一の祇園熊谷うちわ祭2」を今日はお届けしています。引き続きまして新島さんよろしくお願いします。さて先ほど「りんごの独り言」っていうのは銀座区が、叩き合いが終わった後など帰るときに演奏してるといいましたが、実は演奏篠笛リストというか、お囃子リストっていうのを今ちょっといただいて、60曲もあるんですね。レパートリーがいくつかご紹介しますと「子守り歌」「てるてる坊主」ご存知ですか?ラジオ聞いてる方は子守唄って歌えますか。「ねんねんころりよ、おころりよ♪』この歌を笛でやってるということですよね。これやっぱり今の子供たちもこれを聞いてると覚えますよね。
新島 そうですね。
Navi これ当たり前に知ってるかと思うと結構子供も今の子供は伝承の歌って知らないことが多いんですよ。
新島 小学生中学生の子供自体は知らないですけどその親も知らないかもしれない。親も寝かしてもらうとき何歌ったのか、わからない昔は「ねんねんころりよおころりよ、、、」と親がしてくれたけど。これをまたこういうのをどこで教えてるかちょっとわかんないんだけど、学校でも教えてくれる??
Navi なんかちょっと前に教科書には子守唄っていうのはあったかもしれない。だから学校で教えるっていうこともあったかもしれない。今、ちょっと確認してないんで申し訳ないんですけど、でもそれでも我は海の子とは学校で必ず教えて居ると思います。
新島 唱歌は教えてるんだね。
Navi でも今の伝承というかは学校ではやりませんね。今まではお母さんが寝かしつけるときに聴いた歌を、子供ができたらお母さんが歌を伝えていくということになりますよね。
新島 本当にうちで選んでる曲は、日本の独特七五調のちょっと短調的な感じの曲なんです。そういうものがしみじみと聞いてもらいたいと、そして篠笛の澄んだ音色が皆さんの胸の中に収まるという形で。子供たちも一生懸命お囃子していますから。その曲に合わせてお囃子がその都度変わっていきます。
Navi それがびっくりしましたからお囃子に合わせて演奏されるという。
新島 はい。
Navi そうですよねだからそこもすごくもし銀座区の山車を一緒に引っ張ったり、ついてったりしたら、ここにも注目していただきたいってことですか
新島 町内巡行やたたき合い後の帰りや、ほとんどそういう曲をやっていますので
Navi 覚えていた方は銀座区の山車を注目していただけたらと思います。直実節とか青葉の笛とか、これも欠かせないですね、以前は以前は叩き合いが終わった後によく直実節が流れていてあれがすり込まれましたが
新島 昔はお祭り広場でたたき合いが全部終わって、直実節をかけたんです。今かけてないです。
Navi そうでしたっけ、山車がぐるっと回ったときに直実節かかったじゃないですか。
新島 私はかけた方がいいと思います。そして直実節一番終わったらみんなお囃子を始めてして解散になる。そういう形になってほしいです。
Navi 学校は今直実節を運動会で踊っています。だからそういう伝承というか、笛でこれ聞けるということもあるんですね。
新島 だから、直実ってすごく知られています。よその人たちは知ってても、あるいは歌舞伎のファンだとか、あるいは京都とかあっちの方は、直実さんをよく知ってるんすよ。でも実際は熊谷の人たちは直実は知っているけど、直実の内容は知らないことが多い。本当は内容を知ってもらうと、直実公が素晴らしい人だっていうのはわかると思うんですよ。ちょっと熊谷のみなさんに直実さんのことをもう1回見つめ直してもらいたいと思います。
Navi またそれは直実公を知る機会を作ってですか。熊谷でもいろいろな人に直実公の内容を教えていかなくちゃいけないっていうか、知らせなきゃいけないとは思うんですよね。というわけで、今度は何か直実公は熊谷寺と関わりがありますよね
新島 はい、そうですね。
Navi 京都に行った、東京にいったっていうのを聞きましたが、「熊谷寺に行った!」っていう話を聞いたことがあるんですが
新島 はい直実さんの800年遠忌のときに、直実蓮生祭をやるんですよ。そしてその時に「直実大好き会」っていう私なんかは仲間が幾人かいるんですけど
Navi ちょっと待ってください。「直実大好き会」っていのがあるのですか?
新島 そういうグループがありまして。朝日新聞のタウン誌の編集長が頭になってそういうことをやってたんですけどそのときに、銀座区の直実公の山車ができたときに、巡行祭の時、熊谷寺のところを曲がって待ってるんですよ。埼玉信用金庫のところで。熊谷寺のところでふと、山車が一番最初にできた年に直実が載ってますから、直実、熊谷寺の前で1回止めて、記念写真を撮ったんですよ。そしていつかこの中に入れたいなというふうに、直実の本当の菩提寺に入れたいなって思っていました。そしたら800年祭があってだから私はいろんなことでそういう巡り合わせがいいと思うんですよ。Navi そうですよね。
新島 そしてそこの熊谷寺の中に入れることになるんですよ。
Navi ちょっといいですか。800年祭っていう800年忌っていうのは何年ごろだったんでしたっけ
新島 平成19年2007年ですね。
Navi 直実さんが亡くなってから800年経ったというお祭りがあったんですよ。その際に熊谷寺に銀座の山車を入れたっていうことです。
新島 その時には熊谷寺の山門の左側がすごく広く開いてたんです。今は壁ができましたたが、そこへ入れて、ただね、当日雨だったんですよ。直実さんの人形出しただしたんですけど、雨だから濡れちゃうからどうしてもビニールシートをかけて、そこに全国から熊谷さんが集まったんですよ。熊谷の氏族の人たち
Nav 800年祭はお祭りの日じゃないですもんね。熊谷さんっていう人はそこに集まったんですね。
新島 気仙沼の熊谷さんだとかあるいは八王子だとか、あるいは山口それから広島の熊谷さん。そういう人たちが12組ぐらいきました。そしてその熊谷寺にはいったんです。
Nav 雨だったですね。
新島 そうなんですよ。残念だったんですよ。人形は見えないけど、そこにビニールシートをかけて、そこへ熊谷の皆さんに見てもらいまして、そして記念写真撮って、そして私は念願だった直実さんが熊谷寺の中に入れたことで、もう本当に感激しました。
Navi すごいですね。やっぱり菩提寺というか、直実公と熊谷寺は切っても切れないというか。その時は雨が降ったっていうのは、なんかよく聞くんですけども、実は私、西小学校でそのとき教員をやっていて、雨が降らなければ、そこで子供と一緒に、熊谷寺で直実節をやるわけだったんですよ。練習してたんです。
新島 そうすね。西小学校だったんですね。
Navi 子供たちと一緒にその練習をしていて楽しみにしていたら、その日雨で中止になっちゃったんですよ。銀座区の山車は熊谷寺にはいれたんですね。
新島 朝から雨だったですから、カッパ着てみんなで銀座区の車庫から、熊谷寺までもってきたんですよ。とにか熊谷寺にはいったんです。いろいろ批判する人もいますよ。お祭りの山車を何で寺にもってきたんだって。でもね、関わりなくないですから。直実さんが乗ってるんですからね。直実さんが自分のお寺に来ることは何ら文句ないんだと思います。
Navi その話も聞いてやはり直実公が山車の上に載っているのはいろいろな意味があるということですね。これからもきっと直実公があそこにいったとか、ここにいったとかいう伝説がこれから生まれるのかなっていうのが楽しみです。さてここでまた曲に行きたいんですけれども、さきほどの銀座区の篠笛リストの中から、この中の曲ですね。越後獅子の歌。
新島 はい
Navi 美空ひばり 越後獅子の歌 これも篠笛で演奏されているのですね。
新島 はいそうです。
Navi 美空ひばりの歌を若いときから歌ってたんですね。
新島 そうですね。美空ひばりが13歳だったかな、最初のときは昭和25年に歌ったんですね。
Navi ではお届けします。
【曲 美空ひばり 越後獅子の歌】
Navi 時刻は12時40分を回りました。87.6MHz FMクマガヤ 梅林堂提供 やわらか熊谷~僕らが繋ぐ物語~「第35回関東一の祇園熊谷うちわ祭り2」をお届けしています。いい歌だったですね。この歌は本当に子供のときの美空ひばりの音源で聞けたので。
新島 そうですね。このお囃子をやってそれから先ほど言った通り童謡とか唱歌とか、桃太郎とか金太郎とか、あるいは大黒様だとか、そういういろんな曲をやってるわけですよ、民謡とか、その中で子供たちに「どれがいい」聞くと、だから子供たちから唱歌とかそういうのはいいんかなと思ったんですけど。そしたら口を揃えているのは「越後獅子の歌がいい」というんですよ。
Navi 今の子供たちが笛を聞いてこの曲がいいと言うんですね、
新島 ですから、さっき言った通り昭和25年に美空ひばりの歌っているんですけど、やっぱり日本独特なメロディで言うんですか、日本のDNAっていうそういう繋がるところがあると思いますね。それが何となくいいというんです。だって全然知らなかったんですからね。子供たちはほとんどこの中の歌を知りませんから、そして越後獅子を教えるときに、絵を描いてあげて、こういう格好(角兵衛獅子)でやるんだというふうに、頭に獅子をかぶってでんぐり返しをして、逆立ちしたりする。親方が太鼓を叩いて、孤児だとかあるいは売られちゃった、あるいは昔はご飯を食べることができないから、人に売っちゃうと子供を、そういう人たちがこの練習して、角兵衛獅子になるんだと。そういうのを教えてですね。そして歌の内容もちょっと教えるんですけど、一つ一つがみんなわかりませんので
Navi そうですよね
新島 最初はどこで最後はどこかもわかんないし、でもお囃子をやるときに、お囃子の曲が変わっていくわけです。そこのところは勘というのか。何回か練習するともうここのときはこれになるんじゃないってわかるんですよ。そしてその笛があまりにもかっこいいと思って、うちの方ではみんな歩きながら笛を吹いています。
Navi 山車の隣で歩きながら、笛を吹いていくっていうことですね。
新島 それがかっこいいんだかどうかわからないですけどもう小学生のうちから「私も笛ならいたいです。」って中学生も、「すぐあの笛が欲しいんです」って言ってきます。
Navi なるほど
新島 でも笛は高いもんですから、「よく親と相談してくれ」と、ただ、それってうちは二、三十人の子供たちが今笛を吹いています。ですから普通のお囃子のとき、やってるときでも、子供たち大人がお囃子のときは全く別なんですけど子供たちがお囃子やるときは、笛方が六、七人は必ず吹いています。ですから笛の音がよく聞こえるわけです。
Navi だって難しいじゃないですか。本当の篠笛の音はちゃんと練習しないと出ないですよね。
新島 そうですよ。全くならない子もいるんですよ。昔、私が行田に指導にいったらスペリオパイプでと
Navi 学校のリコーダーなんてもんじゃないですもんね。ならないですよね。まず音が綺麗に出てそして曲を奏でるっていうわけでしょ
新島 そうです。そんなの篠笛を夢中で吹いていると目が回っちゃうんですよ。酸素不足で、お祭り中山車の中で吹いていて倒れちゃうってことは何人かあるんですよ。暑くてクラクラしちゃうんですね。それがずっと練習していくとそのクラクラがなくなってくるんですよ
Navi 夢中でやってたらきっとね、苦しくなっちゃっいますよね。暑いし、
新島 うちのせがれが20分30分吹いていると、あの唇が、たとえばホールとかでやってると、乾燥してきますね。口びるがしびれてきちゃうんですよ。湿気がなくなって、ですからそういう点では大変なんですけど、でも何とかこなして終わりにするんですけど、ただそれが普通のちょっと練習ぐらいじゃ、それができないですね。
Navi でもまた、今年の祭りでもそういうのが見られるということで
新島 そうですよね
Navi 子供たちも笛を吹いている、それも見られるということで、いろいろなことを知ると、またお祭りの楽しみ方っていうのは増えてくるのかなと思います。ただ行ってちょっと見るんじゃなくて、見るところっていうのはたくさんありますよね
新島 お囃子にしても、各町ほとんど皆さんどこのお囃子も一つに聞こえると思うんですよ。少しずつリズムが違っているんですよ。手が一つ抜けてたり、一つ多かったり、それから、途中から切り替わるやつが少しずつ変わってます。ですから本当はそれを聞き分けると本当は面白いです。それから太鼓の音色が町内によって違います。
Navi それは去年初めて気づきました。こんなに甲高い締太鼓のところがあったり、大太鼓も高さが全然違うんですね。
新島 そうですね。だからそこは難しいんですよ。小太鼓はあんまり高くしちゃうと太鼓っていう音じゃなくなっちゃうんですよ。木を叩いているような形になっちゃう、その太鼓の革を叩いてるっていう感じがある程度のところにした方がいいですね。
Navi 調節できるんですね。
新島 そうですね。小太鼓はできますが、大太鼓はもうできないですけど、音が低いんだとか高いこともあるけど、そこそこ小太鼓よりちょっと低いぐらいの感じが、私としてはいいと思います。そこら辺がね、その町内の判断です。私がやってる彩鼓蓮というお囃子のグループでは、大太鼓はちょっと小さくなって、ちょっと高いんですよ。
Navi なるほど、
新島 それがいい塩梅な音を出すんです。
Navi その彩鼓連ってでたんですけれど、山車屋台祭研究会ということですよね。
新島 その中に彩鼓連があります。
Navi それがかなり太鼓やお囃子については、研究もされてるということですね
新島 小学生の小さい子が、今、小中学生でやってること全部こなしちゃいますから。
Navi 普段も練習されてるんですね。
新島 してます。
Navi どういう感じでやっていますか?
新島 毎週土曜日行きたいんですけども、その場所が取れないです。市民ホールに行ってそこの実習室ってとこは音を出しても大丈夫です。そこでやってるんですけど、月に2回ぐらいですかね。土曜日の夜6時から10時までね。その間で練習しています。
Navi そんなにやってるんじゃできるようになっちゃいますね。
新島 そうですね。
Navi 2ヶ月に1回ぐらいの練習会参加してやってるんじゃなかなか覚えられなくて
新島 そうですね。でもやっぱりそこにきちんと特に熱心だし好きだから、ただやっぱり普通のこれから新しくお囃子方を集めてお囃子練習する人と比べると遥かに上手です。
Navi そりゃそうですよね。あとそこは銀座区のお囃子をやってるんですか?
新島 銀座区のお囃子やっていますよ。
Navi ですよね。そこはもう精鋭が集まってどんどんブラッシュアップする感じですね。
新島 私が代表やってて、せがれが指導やっています。
Navi だから山車屋台研究会が妻沼の長慶寺やったというのを聞きました。ちょっとびっくりしました。
新島 火渡りの儀式があって、その前に催し事ってことで、お囃子をやりました。今言ったいろんな曲を流して、お囃子をして、そしたら妻沼の方の人たちは、「お囃子って初めて聞きました」っていいました。
Navi そうみたいですね。
新島 いや私もびっくりしました。
Navi もうみんな知ってるもんだと思ったら、そうではなくてびっくりですね。他の地区もこれからもいろいろなところに行ったり、イベントでお囃子をやったりすることが多くなってきていいなって私は思ってるんですけど、いよいよ妻沼の方々に聞いていただいてってことで
新島 そうですね。
Navi もっともっと妻沼の方にも知ってもらいたいですよね。
新島 そうですね
Navi 妻沼は熊谷でお互いにやっぱり知っていただいてって思うと、聖天様のあたりでもやったらいいですね。
新島 妻沼高等学校行ってお囃子やってこともあります。
Navi そうですか。いろんな活動もされてるということで、
新島 やっぱりあちこちいっぱいってます。よそのお祭りの当日、下仁田では仲町っていうところで私達が行って、その山車の上に乗せてくれてっていう、実際動いてんですよ。そこでお囃子やりました。
Navi 銀座のお囃子をやったのですか?すごいですね、前はたたきに来てくれて、今度は叩きに行くこともあるということですね
新島 私の知り合いがいまして、「新島さんぜひやってくれ」ってことで、
Navi そうですか。
新島 普通はねちょっとできないですよ。
Navi お祭りの方もそういう気持ちがあって聞くと興味深く多分聞かれると思います
新島 同じようなお囃子なんですけどうちは、いろんなお囃子をやってますから、もうみんなが耳を傾けてね、シーンとして聞いてましたよ。山車が動いてるんですけどね。
Navi これはすごいコラボと言っちゃあれですけど、広がっていくっていうのは、これからすごくいいですよね。
新島 そうですね。
Navi 聞けば聞くほど出てきてしまってね、今日も全部聞き取れなかったんですよね。そんなわけでこんな時間になってしまいました。本当にあっという間ですねいつも。もうまたまた来ていただけますか?今日は関東一の祇園熊谷うちわ祭2ということで、お祭りといえばこの人 熊谷山車屋台祭研究会会長 新島章夫さんに来ていただきました。今日はありがとうございました。
新島 ありがとうございました。
Navi うちわ祭りまで末まで待てませんね。
新島 はい、頑張ります。
Navi ありがとうございました。