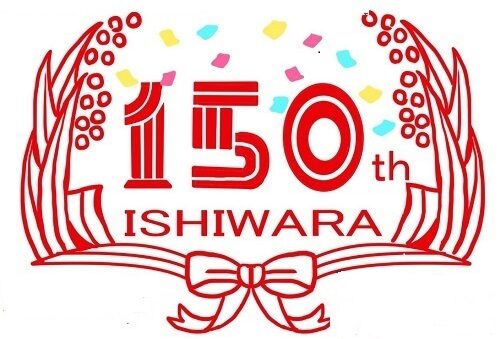さて 5月19日(月)12:00~12:54FMクマガヤ やわらか熊谷僕らがつなぐ物語は?「関東一の祇園 熊谷うちわ祭」と題して うちわ祭のことならこの方 熊谷市山車屋台研究会会長 新島章夫さんをゲストにお迎えして、うちわ祭のお話を聞きます。うちわ祭りまであと2ヶ月あまりとなった今、今までのお祭りこと今のお祭りのことそしてこれからのうちわ祭についてお話を伺います。とっておきのお話も聞けるかもしれません。どうぞお楽しみに!

20250519_12時台
⏰火曜日 2025.05.20 09:23 · 60mins
文字起こし
Navi 時刻は12時を回りました。 AZ熊谷6階FMクマガヤ ワイズコンサルティングスタジオから生放送でお送りします。梅林堂提供 やわらか熊谷~僕らがつなぐ物語~第33回今日は、関東一の祇園熊谷うちわ祭りという題で、ゲストはうちわ祭りといえばこの方。 熊谷山車屋台研究会会長新島章夫さんです。 こんにちは
新島 こんにちは
Navi お待ちしてました。 今日は新島章夫さんに、たっぷりうちわ祭りのお話をしていただきたいと思います。お祭りまであと62日ということなってます。あと2か月ですよ。ワクワクしませんか? 本当にあの去年祭事係っていうのは初めてやらせていただいて、そちら側に回ったのはまだまだ初心者で、まだまだ分からないんですけど、それでもあの3日間のことを思い出すと今までと違うワクワクさですけど、新島さんといえばもう。 長いこと 関わってますね。
新島 そうですね。 私はあの11歳からお祭りに関わりまして。 そして今年で67年
Navi そうですか、もういろんなことがあったでしょうね。
新島 そうですね、お祭りも年々いろいろ形が変わってきまして、まあ特にあの私は小さい時から考えて一番大きく変わっていうのはとにかく山車屋台が綺麗になったことです。 それからあの皆さんの衣装が大幅に変わってきていますね。昔はそんなに今みたいなあんなかっこいい形はしてなかったです。
Navi まず、山車屋台がきれいになったっていうのは、なんとなく自分もその記憶にあります。私も子供の時からうちわ祭りを見てたんですけど、ちょっとそう言われてみれば、なんかキラキラ輝いてきてるかなとか、
新島 そうですね、最近特に伝統的に大切な道具だという考えが強くなってきましたので、改修したり補修したりしてますねえ。 その昔は、とにかく幕をついていなかったり、飾りものもなかったり。 そして本当に柱だけが見えて、そういうところでしたね。山車は後ろに幕があったんですけど、屋台なんかはほとんど飾りや幕がなかったですね。
Navi 飾り物が。 あと、私が思うのは、あの鉦がやたらこう今、光ってるような気がしてならないんですけど、
新島 そうですね、昔から比べると、みんな意識が強くなって、より綺麗にしようってことで、そして磨くようになったんです。昔はそんなに磨いたりしなかったんですけどね。今ずっとあのお祭り前になると子供たちが一生懸命磨いてくれますね。それでピカピカになりますねえ。
Navi 本当にピカピカで、鮮やかっていうか綺麗です。子供時代のその記憶で言うと、山車の数は4つだったと思いますが増えましたか?12と34とつくばと仲町の4つだったって、子供時代の記憶です。
新島 ああそうですね。 増えたっていうのは仲町、12と34と、それから筑波町の4つだったですね。その後は銀座が増えまして、はいはい、それから現在は荒川が平成24年に作りまして、それからその後にまた(H29)伊勢町が山車にしたという。 Navi なんかだんだ! やっぱりこう進化してるんだなって。
新島 そうですね、感じています。 あの屋台には屋台のよさがあるんですけど、まあどっちかというと、山車の方が華やかな感じがしますよね。
Navi そんな形で このお祭りも進化しているということですね。ちょっと話を元に戻しますと、今日、新島章夫さんをゲストに呼ぶのは、ずっと私が待ち望んでいたことなのです。この番組。 始まった時にもそういうふうに思ってたんですけど、私が、新島章夫さんに出会ったのは、お名前に出会ったのはオレンジ色の表紙ので、「 関東一の祇園熊谷、うちわ祭り」という本です。書店だったかどうか分かんないんですけど、この本を見つけた時に小躍りしました。この本は熊谷のお祭りは大好きで、子供のころからずっと 見てきたんですけど、本が出た時に思わず手に取って。 中を見て興奮しました。 「なんでこんないい本があるんだ」と思いました。そして、当時私は熊谷西小学校の教員だったんですけど、この本を見たときに、「これはすごい」と思って、うちわ祭りの教科書にしようと、総合的な学習の時間っていうのが、小学校中学校であるんですけど、そこはテーマを自分たちで決めていいんです。 学校で地域の教材とかっていうんで、迷わず打ち合わせして、 祭りの勉強を学校で授業でできるんじゃないかっていうんで、考えてその時の教科書にしようと思ったのが、この「関東一の祇園熊谷、うちわ祭」です。まず自分で買ってきても、家でずっと読んでしまって、こんなによく書いてあるんだと思っていました。 そして、そこに名前が出ていたのが、新島章夫さん、実際に会ったことがなく、その時に新島さんを訪ねればよかったのに、授業に夢中で子供たちとこの本を読んで、そして一緒に勉強したという記憶があります。 この本はさきたま出版ですけど、どういう経緯で作られたんですか?
新島 そうですねえ、さきたま出版会の方からお話がありまして。 「うちわ祭について 書いてくれないか」って、そういう話がありました。 そこには亡くなった栗原さんとか、いろんな人たちが協力してもらって、「じゃあ、あのそれ書きましょう」ってことで、そういう専門の方たちが来てもらって、打ち合わせをして、その本が出来上がるわけですけどね。 今はオレンジになったんですけど、最初は 表紙が赤だったんです。 それが全部売り切れて再販する時に何かどっか変えないとダメらしい。それで表紙をオレンジに変えるんですけど中をちょっとあの訂正したところもあります。それでオレンジが二版目ですね。 大変売れたんで。 まあびっくりしたんです。子供たちが夏休みの宿題に使うことが多くて、そして子供たちがいっぱい買ってくれたんじゃないかなと思います。
Navi 私は学校にお願いして、勉強に使えるように、図書室に最低40冊、結局80冊買ってもらった気がします。図書の先生に「お願いします。 これ買ってください」子供とかにも「買って!」と頼んだような気がするんですよ。
新島 いや、だから当時あの売り上げすごかったんですよ、
Navi これは買いますよ。
新島 そんなに売れると思わなかったですから、
Navi そうでしたか。 この新島章夫さんという名前だけは、もう目に焼き付けていました。他の方はみんな知ってたと思うんですけど、私はこのお名前だけが記憶に入っていました。この本は屋台と山車がすべて解説してあって、それから巡行の話から何から 分かりやすいです。それから積極的にフリガナがよく振ってあって読みやすいです。
新島 そうですね。ういう専門的なのですから、あの難しいことが出てきますし、神様の名前などやっぱり振り仮名で分かるようにした方がいいなってことで。
Navi 歴史の本とかで、うちわ祭のことは書いてあると思うのですが、あちこち点在していてわかりづらいです。この本は全部集結して、しかも、すごく分かりやすいこの本は本当に素晴らしいです。今でも買えますか?
新島 販売しています。 今は、その先ほど言ったように進化しているので、その内容は 平成13年に作ったものですから、その間に山車が2台増えちゃいましたね。祭りの運営の仕方とかはほとんど変わってないですね。
Navi Q&A方式で書いてあったりして、読んでいただければ、熊谷のことを知らない人、熊谷のことを知ってる人でも、ここまで知ってお祭りに行くと、見方が変わりますよね。
新島 どこのお祭りでもそうですけど、京都で例えばこういう話があります。ちまきを買ったら、ちまきの中に何も入ってなかったとき、「こんなのおかしいだろう」ってそういうことを言ったんですよ。ちまきってお守りなんですけど、だから京都の方ではお祭りを見たり、何かを見学したりする時には、少し自分たちで勉強してもらってからのほうが、より分かりやすい。「もともと餅ははいっていません」とそういう話を言ってました。
Navi 本当はお餅が入ってないものなんですか?
新島 いやいや、そうじゃなくて、京都の八坂神社でずっと昔から出しているちまきは腰に下げて、そして、あるいは家の玄関に飾るものとか、そういう形でやってるもんですから、その中にもちははいらないんですね、
Navi そうだったんですか、それが今はお餅が入っているのはっていう当たり前かと
新島 だから、あのそう、ちまきって普通、あの何かお餅が入っている。お土産で買ってきますから、そういうもんだと思ったんですよね。 昔のことは、スサノオの尊蘇民将来の物語とか、そういうところで出てくるんです。
Navi そうでしたか、私も今初めて知りました。 ありがとうございます。知っていると、ますます楽しくなりますよね。
新島 この本で学校の生徒とそれから学校でなんか授業はいやってるってことですけど、私はもう、熊谷東小あるいはそれから、南小とか西小とか、それからいろんなとこ行ってます。東小はもう30年ぐらいずっと行っています。 今でも行ってます。昔は総合的な学習の時間は5時間取れたんですよ。 それで今は3時間になっちゃったんですよ。昔は1日目はお祭りの講義をします。 歴史的なそういうもの、それから2日目はお囃子をします。 3日目は山車小屋にみんな来てもらいます。 そして山車の上にみんな乗ってもらいます。 それをずっともう30年ぐらいやってます。
Navi 知りませんでした。 今でもやっていたのですね。 私、東小学校に1年だけですが、勤めたことがあるのに、なんでその時知らなかったんでしょう。 本当に失礼いたしました。やっぱりそこがルーツですね。
新島 毎年5年生がやってたのです、
Navi じゃあ、銀座の山車に乗った経験を子供たちはしているということですね。
新島 そうです。 だから、あの山車の上に乗せたいっていうのは、私が思うには、東小の地区に山車のお祭りのやってない地区があるわけです。中西とか上之とか、 それはもう入ってないからで、子供たちが山車っていうのはどういうもんだかもわかんないし、実際に高さがどのくらいのかってもわかんないから、ぜひ乗ってもらいたいと思いました。 ところがあの「僕は、お祭りの地区じゃないんですけど、山車の上に乗っちゃっていいんですか?」っていう子供がいて、かわいそうになっちゃって
Navi そう言いますよ。
新島 「なんで?乗っていいんだよ」っていって、 そして上に乗ってもらって、でも乗ったらもう降りるのがみんな嫌なんですよ。
Navi そうですよね、
新島 約百人ぐらいが、 3人座る太鼓枠があって毎回乗るわけですから、3クラスぐらいですけど、それで時間かかっちゃう。
Navi それはそうです、狭いところで、登ったり降りたり、
新島 そうなんですよね。
Navi でも乗れる経験を30年もやったんですか?
新島 そうです、 高いですから、はしごで上がるんですよ。 ですから、降りる方もはしごがあって ちゃんと大人がそこに構えてもらっていて、危なくないように それでみんな記念写真を撮った。
Navi 新島さんやっぱりさっき「乗っていいんですかっていう子」がいるって言ったけど、それは みんなそう思ってきています。 私が子供の時にその屋台とか山車に乗るなんて、とてもできなかったですよね。 乗っちゃいけないっていうか、「乗れないよ」っていうふうに伝え聞いてて、地区外とかっていう言葉はもう耳に残ってるぐらい。 それを新島さんはもう 30年を壊して、
新島 私自体も、11歳から祭やり出すんですけど、山車の上に乗れるっていうのは、それまでもう山車の上に乗りたくて乗りたくてしょうがなかったんですよ。それは夢のまた夢だったんですよ。 ところが、熊谷市で、一番最初に銀座からお囃子を始めようってことになるわけですよ。 その時は、昔は外からお囃子がきてたんですけど、本庄、あるいは深谷とか岡部とか、そういうところからお囃子方が来てたんですよ。それをいろんな状況が起きてきて、「それじゃあ自分のところでやっちゃおう」ってことで、銀座区が一番最初に始めます。
Navi ちょっといいですか、もう一度先ほどのお話をするとですね、もともと熊谷のうちわ祭りのお囃子は、熊谷の人がやっているのではなく、 深谷や本庄の人がたたきに来て、そして、それを皆さんで見ていたということを初めて熊谷の人が自分たちでやろうとしたのが銀座区なのですね。
新島 それが昭和32年です。
Navi 私生まれてなかったんですよ。 38年生まれなんです。
新島 昭和32年で私は11歳ですから、そこからじゃあ熊谷で始めようっていうので、その時は、あのよそから来てたお囃子叩いていたのはみんな大人だったんですよ。ですから大人を集めたんですよ。その時に初めて大人を集めたんだけど、私だけ子供でなぜかそこに行くんですよ。というのは、うちの隣のおじさんが若連の親方だったんですよ。 それで、「おめえは特別にちょっとあそこへお囃子の練習始めるから、いけ」って言われたんですよ。 まあ、それは嬉しかったですね。 Navi ですよね。
新島 そしてみんな大人なんですよ。 ところが、もう私は小さい時から、もうお祭りの山車を引くことも好きだったんですけど、とにかく、小さい時から引いてて小さいから夜になると眠くなっちゃうんですよ。 昔は、外にどこにでも井戸があったんですよ。井戸で顔を洗ってね、目を覚まして。 そして、やったんです。 それでは、いつかあの山車に屋台に乗りたいなと思ってたら、その話が来るわけです。 まあ、それはもうそれは嬉しくて。 毎日こっちはもう面白い、やりたくてしょうがなかったですから、もうお囃子もすぐ覚えちゃったんですよ。 そしたらこれは子供に教えた方がいいかなという 大人は覚えが悪いと。 もちろん大人もやったんですけど、それで子供は自分がやった次の年から幾人かやるようになります。
Navi そうですか、なんか今では、子供はたたけるのが当たり前っていうけれども、その前は子供も叩けなかった。それは子供たちがたたけるようになった、その第1号が新島さんですね。
新島 はい
Navi それはいい話を聞きました。
新島 いや、もう嬉しかったですね。 あの一番最初に叩いたその感触っていうか、それからその山車がガクって、動いた瞬間はい、これはもうしびれました。 もう体がぞくぞく震えてる
Navi あの新島さん、私も実は去年初めてそれを経験しました。すって動くときのね。 ぞくぞく感っていう。それを60年前に していたのですね。同じ経験だったと思います。ぞくそくしました。 動いた時に揺れて、
新島 いや、もうすごいですよ。
Navi 叩けるのも素晴らしいし、動くのも素晴らしいですよね。 いやもう本当に貴重なお話をいただきました。 さて曲に行きたいと思います。 石川さゆりです。 これお祭りの歌なんですね。
新島 はい、風の盆ってすごくいいお祭りです。静かな
Navi ということでお届けします。 風の盆恋歌。
【曲 石川さゆり 風の盆恋歌】
Navi 時刻は12時24分を回りました。 梅林堂提供 やわらか熊谷~僕らがつなぐ物語~関東一の祇園熊谷うちわ祭りをお届けしています。 ゲストは熊谷山車屋台研究会会長の新島章夫さんです。 さて、新島さん。 あの先ほどの貴重なお話を、聞かせていただいたんですけれども、まあ、うちわ祭りの逸話というと、60何年の歴史じゃないですけども、新島さんが経験したいろんなことがあると思うんですけれども、どんなお話、ちょっとお聞かせいただけたらと思いますけど、
新島 私の中で一番すごいのは、屋台から山車になる時です。この山車をつくるときに企画を全部任されまして、山車屋さんとの交渉とか、形、そういうデザインを全部任されました。
Navi いいですか? 新島さんじゃあここでまた一回もどりますが、 このお話は、銀座区は、屋台だったのが平成6年に山車に変わった時のお話ですね。
新島 そうです。
Navi 私、この銀座区はずっと屋台で見ていたのが山車になって、その出来上がったものを見た時にもうびっくりしました。 そのお話ということですよね。すいません、途中で取り止めちゃったんですけども、平成6年に銀座区屋台から山車を新しくしたお話ですね。
新島 あのその前の年、平成5年、4年ぐらいからもう屋台が古くなってるから、新しく作ろうとしました。はじめは屋台という構想だったんですよ。 でも私は山車にした方がいいという話をしまして、そしていろんなところの山車の写真とか何かを町内で見せて、そして金額的なものを見せて、当時としてある山車屋さんで見積もって6000万円ぐらいするというのですけど、3000万円ぐらいでできるってところへお願いして作ったんですよ。そして、その予算の中でいろいろ注文して、だから大工さんが非常に困ったそうです。いろいろ要望すると「まあしょうがねえな」って言われて、それでやってもらったりして、平成6年の年番が来る年の6月にできた。 そしてマロードインのところの庭に山車を置いて、そして式典やった。
Navi そうですか。 もうこのだしを私初めて見たときに、あのびっくりしたポイントは大きく2つありました。 1つはですね、山車のところに、下に屋根が付いてますね。 はい、あれが「あっ、新しい」と思ったんですよ。
新島 はい、あれは最初から構想上あったんですね。 ああいうのは他にもいくつかあるんですよ。 鉾のところにあの屋根がついてますよね。 そのひさしみたいに作るわけですよね。 裳階っていうんですけれども、その裳階をつけて、熊谷の山車は全部、裳階なんてないですから、その後ろ側にぼんぼりもついて、なおかつ下に軒ちょうちんが下がるんですよ。そうするとすごく華やかわけですね。
Navi 確かにそう思いました。
新島 そしてあのその後にまた1つあの問題が起きるんですけど、人形は熊谷次郎直実を乗せました。
Navi もう一点はそこです。私もびっくりしたのは、人形が熊谷を代表する、あの熊谷次郎直実公が出てきた時に興奮しました。 「うわっ、すごい」と思って、これなんかまだありますね。
新島 私は初めから直実を乗せようとしていて、考えてたんですね。 そしてまあ、あの町内の人たちもそれいいんじゃないかという形で、そしてあの人形を作ります。そして実際にあげたら「なんだあの人形は」と、熊谷の市民、市民というより、お祭り関係者ですね。 そしてあの上の方の方たちもいましたし、それが一般の人たちもいましたけど。「 あんなものなぜ載せた」という、私のところに電話が何本も来たんですよね。 「あんなものなんで載せたんだ」と、「あれは武士じゃないか」「だいち坊主になったじゃねえか」と「あんなものをお祭りのせるばかいるか」と私のところに、電話は何本もきました。 そして街中でもそういうさわぎをしたんですね。 ところがなんで直実がいけないかってことなんですよ。熊谷はそれまでにさっき言った山車が4台あって、スサノオノミコトと手力男のミコトからヤマトタケル。それから神武天皇と全部あの昔の神様が載っているわけですね。それだから熊谷の人はみんな人形は神様が載らなくてはおかしいんじゃないかという判断をします。それはまったくの間違いで、この人形というのはそこの町内の象徴、あるいは町の象徴、あるいは町内の思想だとか、そういうのも含めてみんなそういうのを作るんですよ。ですから、直実が悪いってことは全くないんですけど、それが理解できなくて。 あの残念で、全く残念で、もう本当にその頃悔しくて寝られなかったんですよ。 なぜ知らないんだと。 そういうことは、実はね、よそにはもちろん、武将はいくらでもいます。頼朝もいますし、家康もいます。それからもう1つのちょっと下の方へ来ると国定忠治とかね、その人形を乗せてるところもあります。 それから「坊主になったじゃねえか」 といったら川越には、武蔵坊弁慶が載っています。元々坊主です
Navi 武蔵坊ですね。
新島 そういうふうに、いろんなところがあるんですけど、歌舞伎で直実はヒットします。それをあの多分、神様きり見てなかったからそう思うんですよね。 実に熊谷直実っていうのは、実に素晴らしい人ですよ。歌舞伎の中でも一番多く演じられている、(一谷軍記熊谷陣屋)歴史上で演じられているのは熊谷直実なんですよ、 ですから、それも誇りを持って私はあげたんですよ。それがそういう批判がある。 今でも幾人かそういう人はことを言ってる人がいますけど、最近は言わなくなりましたね。
Navi 私はもう本当にこうゾクゾクしました。 あの直実公があがったぞと思って。自分もその固定概念で、そのなんとかノミコトとかっていうのは上がるもんだと思い込んでいて、熊谷以外の祭りをそんなに私も見に行ってなかったので、それを知らなかったと。直実公が上がって銀座のあの「もこし」のついた山車を見た時には、「新しい時代が始まった」のかなって思いました。
新島 そうですね、お祭りっていうのはいつも私言ってるんですけど、伝統というのは伝統って初めから伝統ってないんですよ。 どんなものでも最初はあるわけですから。 その時に伝統っていうのはないんですよ。伝承っていうのは、それを伝えてくるね。 伝統というのは、それが何年か経った時に伝統という形になるんですけど、その伝統ということで、一番大切なことは必ず守っていかなくちゃならないもの。 それから、新しくどんどん変えていっていうものはそれがあるわけですよ。 ところが、大体の人たちがその祭っていうのはこうなんだと、今知っているお祭りっきり考えないですね。 ですからこういうことしちゃおかしいとか、そんなことないですよ。例えば熊谷のうちわ祭だって神事っていうのはそのままで、あの過去の昔から変わってないですよ。つけ祭りっていうのは山車が出たり、いろんなことをやることは、それはどうにも変わってくるはず。 たまたま熊谷の場合は明治24年に本町34が山車を買ってきたから山車の祭りになってきたんですよ。 もしこれが山車じゃなくてねぶたみたいなもんだとか、あるいは踊りみたいなものが入ってきたら、そのそういう形のうちわ祭になります。 ですから、山車自体初め買ったから山車の祭りになってきます。でこの界隈もどっちかというと、皆さんは熊谷のところを参考にして、いろんなことをまねてお祭りやってますけど、 でも古いのは本庄とか寄居とか、そこのへんはもっと古いですから、幕末からもうそれから明治の初期からやっています。熊谷が本当に山車の祭になるのは明治24年からです。 ですからまだまだ新しいお祭りですね。
Navi そうでしたか、これをやっぱり大事なことですよね。 今、あの聞いていて思ったのは、 始めた人がいるっていうこと。 それからやっぱり、伝統と伝承っていう話も聞いてですね、じゃあ伝統を作っていくというか、まあ、ある程度こうね、あの盛り上げたり、小さいことになっちゃうんですけど、そのあの、ピカピカに磨いてるっていうことも、なんか変わってきていることだなと自分なんか思っちゃう
新島 そうですね。
Navi 他のお祭り行くと、あの鉦が磨いてないところを見ると、熊谷はもうピカピカ。 これがまた新しいあのスタイルなんだなって思ったりとか、
新島 そうか、まだね、ピカピカになってないもんね、
Navi あと袢纏が、鮮やかになってますよね。
新島 そうですよか、衣装もね
Navi あれもじゃあ、例えばなんとか染めじゃないといけないとか、そういうのはないということですよね。
新島 まあ、そうですね、
Navi だからバリエーションがあって、進化して華やか。似たようなお祭りは確かに近くにあるんですけど、華やかさというと、熊谷はすごく華やかな気がしそうですね。
新島 女性が出てきたり、前に出た女性が出てきたり、昭和50年にうちの銀座区で私が女の子連れてきては、最初にそのちょうちん持ちをさせたんですよ、それからずっと今、各町やってますけど、
Navi やってますよ。じゃあ、どこからかやっぱりスタートして、銀座はかなりこう、そういう点では先進的なことをそうですね。
新島 私が特にいろいろなことをやりましたけどね。 いろんなことは
Navi まあ楽しいとか盛り上がるとか、皆さんのそういうところをこう。 あの考えていらっしゃるから、もう、先ほど、その東小学校の子供たちが山車の上に上がっているのを、30年前からやっていたっていうのを聞いただけでも、これから皆さん、そういうことでこう親しんでいけたら、お祭りはますます楽しくなっていきますよね。
新島 それから市立女子高校は、15年ぐらい授業でやってました。交流していたNZのインバーカーギルの生徒が主張できるのに、熊谷の生徒が主張できず、海外に誇れる文化を教えなければと女性校長さんが来宅されました。
Navi あ、そうでしたか。 新島さんに聞くと、今のお話はもう銀座のところから動いているのがわかったのですが、まだまだもう1個ぐらいなんかありそうな感じがするんですが、京都に銀座の山車を持っていった話をちょっと 聞きたいです
新島 そうですね。これは、あの京都が平安遷都1200年平安京から794年から1200年たったんですね。 ちょうど、平成6年じゃあ、年番の時です。 年番で山車が新しくできて、その時に京都で山笠巡行しようじゃないかといいう話が出ました。 前の年から話が出てたんですけど、 執行する日が7月23日です。京都で、熊谷で7月20日21日22日でやってて、23日の午後一時半までは還御祭を熊谷でやってるんです。 お神輿を夜中までやってます。 それで「23日は無理だろう」ってことで、ええ、前の年番町が筑波でうちが平成6年の銀座ですから、その時に話が来た時には、筑波町にまだ年番があったんですよ。 で、当然そのお祭りの翌日は、ちょっと無理だというということで断っちゃったんです。 私は京都にちょっとつながりがありますので、「新島さんなんで断ったんだ」って言われたんですよ。 それで翌年になって、その話はまた改めて宮司のところへ来るんですけど、八坂神社の宮司が来て、宮司も「これは無理な話だから、物理的に難しいんじゃあ、断っちゃべってことで新島断ったよ」って言ったんですよ。 「そんなことは大丈夫ですよ」って私は言って、その話を京都に私が直接電話して、「なんとか行きますからね」ってことで行くことに決定したんです。 それからこの銀座の町内をまとめなくちゃいけないんで、いろんな総代さんとか、いろんな人たちに話をして、こういうわけで「京都へ持っていくんだ。 お祭りの次の日なんだ」となぜかっって言ったら熊谷次郎直実さんは京都で大番役って役を二度やってるんですよ。皇居をお守りする役、京都に行ってたか、京都に由緒あるお寺を作ったとか、寺がいくつもあるんだといって。 「どうしても京都へ帰してやろうじゃないか」という話をしたんです。そうしたら 皆さんのってくれました。よしじゃ、お前に任せるということで、ただお祭りが22日の夜終わりましては、10時半ごろ山車が帰ってきます。そのまま山車は解体します。
Navi 解体ですね。
新島 解体っていってもね、そんなあの細かくなくて、上のところと、下の車輪とか外して、そしてトレーラーに積む。トレーラーも低いんじゃないと通れないです。 それで低いのを探しては当時45センチぐらいだったかな。 今あの30センチぐらいあるんですけど、それに積み込んで、私はその頃その時 祇園会の会長をやってました。それでどうしても環御祭やらなくちゃいけない。一時半ころ「ここで俺は帰らせてもらうよ。 皆さんあとよろしくお願いします」とで頼んで帰ってきて、バスが待ってていでバスに乗ってすぐ京都に向かったんです。 京都の四条通り、八坂神社の前のところの四条通りなんですけど、そこに、お昼12時までには、セットしなくちゃいけなかったんですよ。私たちが着いたのは11時半ぐらいに着いたんですけど、山車はまだつかなかったんです。それで先に行ってるんだけど、 そしたらよその地区の山車は全部セットされて、出来上がったんですよ。 いろんなところから来ているのはもうできていて、14箇所から来て、青森から九州まで全部出来上がってたんですけど、あとから着いてそこから組み上げたわけですよ。
Navi もう時間がないですね。
新島 京都テレビがもう全部取材終わっちゃったんですよ。「あと、熊谷の銀座さんですけど、早くあの組み立ててください。」京都テレビはなんとか間に合わせたいというのがあったんですね。その道中、なんとかいろんな問題があったんです。高速道路の許可を取るとか、なんか、
Navi でもそれをやるかやらないから、もうチャレンジですよね。
新島 いや、本当にね、これ、あの途中であのまあ、とにかく行くまでにちゃんとあの交通事故でも何でも1つでもあると時間が遅れちゃうから。もうそれがないようにないように、ただひたすら祈ってましたね。
Navi そうですよね、だって、何があるかわからないですよね、
新島 長い高速道路で何かあったりしたら、でもう間に合わなくなっちゃうから。なんかそれが全くなくて、 12時前についたってことは、それでもう約束通りですから奇跡ですね。もう本当、それは本当にヒヤヒヤしました
Navi 直実公が馳せ参じた感じですか。 あの京都に。
新島 それで山車が出来上がって直実がするするするって上がって見えた時に京都を眺めるわけです。でも、あそこであの本当はその中で回転はできないです。 どこに要するに、よそはみんな4輪ですから、でも、3輪だから、その囲いの中のところに飾ってあったんですけど、ぐるっと一回りできる、
Navi なるほど。 また解説になりますけど。 他の屋台や山車っていうのは、本来4輪で、その場で回すのは至難の業ですよね。 その場で回るなんてできないです。 でも、熊谷の山車は3輪で舵が切れるので、その場でぐるっとまわれる。そして、直実さんも一回り京都を見渡したと、粋な動きですね。 他にはできない熊谷の山車の特徴ということですよね。
新島 そうですねえ、
Navi でもまあ、そこに行った人たちは、ほぼ寝ずにいったような状況で
新島 そうです、だから還御祭ってのは、あの最後にお神輿を返す。そこで白い半纏を着て、みんなびしょびしょなんですよ。汗でみんなうちの前で水で洗って絞ってバスの中で干していったんですよ。
Navi だって皆さん祭り、3日間暑くてね、疲れてるのにもそうですね。 でもいったんですね。
新島 だからまあ、疲れがすごかったんで、それと時間の問題でしょう。 それは競争でしたね。
Navi やり遂げたという。 それは すごいことでしたね。もうそれを考えただけでもまず運ぶとか、それから熊谷の人がそのお祭りのすぐ直後にそれを成し遂げたっていうことは、本当にすごかったですね。
新島 そうですね。 あのバスは、2台ぐらい行って、引き手が必要でしたね。 向こうでも京都でもボランティアの会がいっぱいありまて、「熊谷さんあの大学生は何人ぐらい欲しいですか」とか、向こうはもうすごい協力体制で「屈強な大学生男子を人20人でも30人でもそろえましょう」って、「うちの方は引き手がいるから大丈夫です」と。そういうふうに京都は真弓さんって当時八坂神社の宮司ですけど、これは京都府と京都市と八坂神社で同時開催にしたわけですよ。京都の八坂神社は、これが失敗しちゃったら大変なことになっちゃうんですよ。 全国ですから。 それで前の日は台風が来るということで、翌日、巡航する時にその偶然台風がそれたんですよ。
Navi じゃあ、そこは台風があったということだったんですね。
新島 そうですね、奇跡ですね。大分から来てる山車は、高さが20メートルぐらいなんですよ。それが台風だったら、もうたちまち倒れちゃいましたよね。
Navi でも、そこは大丈夫だったということですか?
新島 大丈夫だったんですよ。
Navi 新島さんあっという間にも時間になっちゃいましたよ。 もう本当は今年のうちわ祭りとか、いろいろ聞きたかったですけど、あの時間になっちゃいました。 またまた来てくださいね。 ということで、今日はですね、関東一の祇園我が家うちわ祭りということで。 うちわ祭といえばこの人、新島章夫さんに来ていただきました。 今日はありがとうございました。
新島 ありがとうございました。
Navi また 来てください