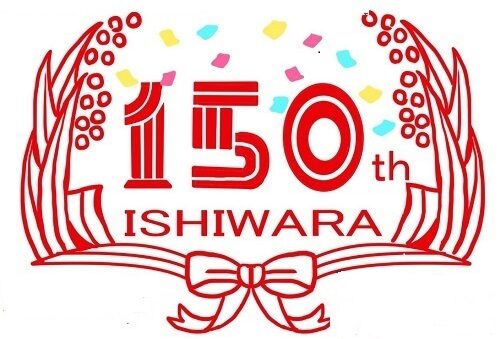2025年4月28日(月)12:00~12:54
梅林堂提供 やわらか熊谷 ~僕らがつなぐ物語~
ゲスト 蛭間健悟さん 熊谷市市史編纂室




文字起こし
Navi 時刻は12時を回りました。AZ熊谷6階FMクマガヤYZコンサルティングスタジオから生放送でお送りします。月曜のお昼は 梅林堂提供やわらか熊谷僕らがつなぐ物語をお届けしています。今日は、第30回斎藤実盛と、妻沼聖天山というテーマになります。この度3月に「マンガ斎藤実盛と妻沼聖天山」っていうのが出てきたんです。熊谷市教育委員会から発行され。熊谷市内の小・中学校の児童生徒に配られたんですけど、ラジオをお聞きの方はご存知でしょうか?お家にありますか。今日はこちらのマンガ斎藤実盛と妻沼聖天山を主に作っていた熊谷市市史編さん室の蛭間健悟さんにゲストでお越しいただいています。蛭間さんこんにちは、
蛭間 こんにちはお世話になります。
Navi どうですか、スタジオは
蛭間 緊張しますね。
Navi 蛭間さんラジオFM熊谷は初めてていうかそんな感じですか。
蛭間 初めてです。
Navi そうですかもう蛭間さんが出ると言って楽しみにしてるっていう方の声を何人も聞いています。
蛭間 いやいや
Navi まず、蛭間さんのお勤めの熊谷市市史編さん室っていうのはそもそもどんなところなんでしょうか、教えていただけますか。
蛭間 はい。熊谷市教育委員会では「熊谷市史」という本を出してるんです。歴史の本なんですけれどもその本を作るというのが目的の部署なんですが具体的には古文書を集めてきて、調査をしたりとか、あと仏像とか、石造物を調べたりとか、あとは編集の先生方がいるので原稿を集めて本を編集するというような仕事をしています。
Navi なるほど。最近出た熊谷市史の一番最近のテーマっていうのは何だったんですか。
蛭間 そうですね。昨年度、昨年3月に仏像仏画2という本が出まして、そちらは熊谷市内の仏像の調査を全地域でやってますので、それをまとめた本になります。
Navi あの蛭間さんは、どちらのご出身なんですか。
蛭間 元々大宮にいたんですけれども、中学生のときに妻沼に引っ越してきまして、それから、基本的には熊谷におります
Navi 中学校のときに引っ越してこられると、そうですね、何中ですか。
蛭間 妻沼沼西中です。
Navi 妻沼西中出身ということですね。その後市役所に市の職員として入られたっていうことですか。
蛭間 そうですね。
Navi 学芸員とかそういう感じなんです
蛭間 そうですね。学芸員資格は持ってます。
Navi 大学ではどんなお勉強されてたんですか
蛭間 大学では日本の中世史っていう武士のいる時代、まさに実盛とか直実の時代ですけれども、その時代の勉強していました。
Navi なるほど、それで大学卒業して、熊谷市役所とか市の職員に採用されたっていうことでよろしいでしょうか?ずっと市史編さん室?
蛭間 いや、最初の5年ぐらいは妻沼町だったので、社会教育課とか公民館に行ったんです。合併して熊谷の図書館の3階の大井さんがいるところに行って、その後は市史編さん室におります。
Navi なるほど大井さん蛭間さんとすごい学芸員さんが、大井さんも中世ですよね。
蛭間 はい、同じ年なのでそうでした。
Navi ちょっと2人のエースが今、市史編さん室と図書館にいるということですね。
蛭間 エースは大井さんだけです。
Navi また、謙虚にこういっておられますけれども、まさに二人のエースですね。さて今回、この発刊されたマンガ斎藤実盛とマンガ斎藤実盛と妻沼聖天山の発刊された経緯を簡単に教えていただけますか。
蛭間 はい。熊谷市では熊谷の偉人についてもっと知ってもらおうということで、偉人のマンガを作るというシリーズを今進めているんですけれども、昨年度、直実・蓮生物語が出まして、第2弾ということで、誰を取り上げるかといったらやっぱり実盛とあとは聖天様かなと思いまして。この本を企画しました。
Navi これは本当に内容が、たくさん詰め込まれてますけれども、皆さんに、実盛公のことはだれが知っていますか?と聞くと「やっぱり蛭間さんだよ」という話をたくさんの方が言っていました。このマンガを作りながら「思い」とか「大変だったこと」とかっていうのはありますか?
蛭間 そうですね。思いはやはり斎藤実盛という人物が全国的に見ると、直実とか畠山重忠と並ぶような偉人なんですけれども、熊谷市内では妻沼地域以外ではそれほど知名度がないといいますか、やはりそれはちょっとなんでしょう歴史を勉強してるものとして寂しいので、ぜひ皆さんに知ってもらいたいなという思いで作ってます。
Navi それは私も実は、思っていて、熊谷の小学校にずっといて、妻沼の小学校に行ったんですけれども、やっぱり斎藤実盛公のことについて、申し訳ないですけど全く知らなくて、小学校に行って子供たちと一緒に聖天様を見たらですね、その像があって、そこにいろいろ書いてあってそれから知ることになったんです。そしてそれを知ったら、すごい方だったんですね。一言で言うと斎藤実盛公はどんな人ですか。
蛭間 そうですね。実はその人そのものっていうのは、なかなかこの時代の人物だと、古すぎてわかりづらいんですけれども、平家物語で作られた実盛像っていうのは「ちょっと知的で、義理深くもある武士」かなとは思うんです。
Navi 知的ということですね。あの像で見ると、髪の毛を染めている姿にびっくりしちゃって一体なんで髪の毛を染めているんだろうとか、それからやっぱり源平の戦いで最初は源氏だったのに最後は平氏で、でも直実公もなんかも、平氏に行ったり源氏に行ったりしてたんですよね。だからこの時代っていうのは本当に生き延びるのが難しいっていうのだけはよくわかって、授業でも子供たちに説明するのは難しいなと思っていましたが、マンガになったっていうのは本当に親しみやすくて、子供だけじゃなくて、やはり大人にもわかりやすいです。
蛭間 はい、取っ掛かりとしてはわかりやすいようになってるかなと思うんですけど、
Navi この本何冊ぐらい今回あの印刷されたのですか?
蛭間 1万6000部ぐらい印刷したんですけれども、そのうち小・中学生に1万3600部配ってますので、残りは2400部となっております。
Navi なるほど2400部ですか。これはですね、これはどこで手に入るんでしょうかね。
蛭間 そうですね。まずは市役所と市史編さん室と市立熊谷図書館、あと江南文化財センター等の市内の施設と、あとは各書店でもご協力いただいているところに置いてます。
Navi 例えば各書店っていうと、どこの書店ですか?
蛭間 須原屋さん八木橋さんのですね。あとは戸田書店さん、あとは妻沼の書店で修文堂さんとむすぶん堂さん。こちらにも置いていただいています。あとはこの本は聖天様にも置いていただいてますので、
Navi 一冊500円、これは、子供たちには全部無料で配布したんですけども。500円以上の価値はもちろんあって、私が実は一番心配しているのは、配られた方、児童生徒です。私は直実蓮生物語が配られた時には、まだ学校の教員だったんですけど、配られたら子供たちは家へ持って帰って、しまっちゃったんですよ。先生たちも忙しくしてほとんど読んでないんです。だから「読んで」って言ったんですけどしまっておかれていることが多いのです。この熊谷の偉人シリーズは素晴らしいんですけど、やっぱりいろんな人に目に触れてもらいたいし「知れば知るほど好き」になるっていう市長のさんの言葉があるんですけど、やっぱりもっと紹介すれば、もっと価値が出てくるかなと思ったので、私は改めて蛭間さんに来ていただいてお話をしていただき、このラジオをお聞きの皆様を中心に知っていただきたかったのです。そして最近ですね、埼玉新聞で記事が出ました。4月26日土曜日「斎藤実盛と妻沼聖天山をマンガに」ということで埼玉新聞でも紹介されております。そこにも、問い合わせ先とか書いてありますので、今日このラジオ聞いてですね、ちょっと手に入れたいっていう方がいましたらですね、あと2400ですか?
蛭間 そうですね。でもそれなりに売れてますので、
Navi と言ってるということは減ってますね。では気になる方は早めにお手に取っていただけたらというふうに思っています。さて、ではここで、曲に行きたいと思います。蛭間さんのリクエストということであいみょんのマリーゴールドをお届けします。
【 曲 マリーゴールド あいみょん】
時刻は12時16分を回りました。AZ熊谷6階FMクマガヤYZコンサルティングスタジオから生放送でお送りしています。月曜のお昼は梅林堂提供 やわらか熊谷~僕らがつなぐ物語~今日はですね、第30回斎藤実盛と妻沼聖天山のマンガについて、今日は、市史編さん室の蛭間さんにお話を伺っていますよろしくお願いします。
蛭間 よろしくお願いします。
Navi さて、ではこのマンガ、斎藤実盛と妻沼聖天山のエピソードにしたがって進みたいと思うんですけど、10個のこのエピソードがあるんです。今回はこの10個っていうのは大体どんな感じで選んでったっていうか、バランスっていうかを考えてたんですか。
蛭間 そうですね半分は、やっぱり実盛の話にしたかったので、10のうち5は実盛にして、斎藤実盛の子供の話をちょっとしたかったので1話入れて、あとは江戸時代の聖天堂と貴惣門ができた話を入れさせていただきました。
Navi 私妻沼小学校で子供たちと「聖天様マスター」って言ってあの聖天山のガイドをする勉強を総合的な学習の時間でずっとやっていたんです。それなんで私も勉強をしたんですが、なんとこの10個のエピソードのうち私が知っているのは3つでした。
蛭間 そうですか。
Navi はい。もうちょっとちゃんと勉強してればよかったので、私はこの10個のエピソードを改めてわかってよかったと思っています。10個のうちまず前半5つは斎藤別当実盛公ですね。ところで斎藤別当実盛公の別当ってなんですか?
蛭間 別当はですね、はっきりとわかっていないんですけれども、何かしらの長官っていう意味です。今で言う県レベルの役所の長官かわからないんですけれども、長官を示している。
Navi なるほど、将軍じゃないけどそういう役割なんですかね別当は。
蛭間 そうですね役割ですね。
Navi わかりました。呼び名に役割が入ってるということですね。
蛭間 はいそうですね。
Navi 前半は斎藤実盛ということなんですけれども、まず 実盛公が駒王丸を助けるというストーリーが1個目になっています。駒王丸っていう人が大事な人ですよね。どんな方ですか?
蛭間 そうですね、後の木曽義仲という人物になるんですけれども、源頼朝のいとこにあたる人です。
Navi 木曽義仲ってやっぱり有名ですよね。源義仲っていうことですよね。
蛭間 そうですねはい。
Navi その時代は源平もそうですが、源氏同士の争いを結構してたっていうイメージなんですかそうですか。
蛭間 そうですね。源氏同士が一つにまとまらずに、例えば武田氏の甲斐源氏とか茨城の佐竹氏とか、そういったいろいろな源氏がいるんですけれども、その中で最後まで頼朝に楯突いた人というか、最大の反対勢力っていう感じに最後なっていく人物が木曽義仲です。
Navi そうですか。でも競い合って、そして源氏は武士の世の中を作るっていうのは小学校でも中学校でも歴史で勉強したと思うんですけれども。その駒王丸を助けるっていうことなんですね。斎藤実盛公は源氏だったんですね。
蛭間 そうですね。最初は源氏側ですね。
Navi 最初はっていうことは、最後は何か平氏になるっていうのを私は勉強して子供たちに教えたんですけれども、助けるっていうのは、駒王丸がピンチだったのですよね。どんなピンチだったんですか。
蛭間 そうですね。ちょうど、源氏同士の戦いが行われまして、すごく複雑なんですけれどもマンガだと9ページに載せたんですけど、頼朝のお父さんの義朝と頼朝のおじいさんの為義っていう人が対立してまして、この2勢力がぶつかると、おじいさん側に付いてたのが義朝の弟の義賢(よしかた)っていう人なんですけれども、その息子が木曽義仲でした。
Navi なるほど、源氏同士争っているところなので、駒王丸は命のピンチだったんですね。
蛭間 そうですね。
Navi そもそも斎藤実盛公は、この熊谷っていうか妻沼で生まれたんじゃないんですよね。スタートは?
蛭間 そうですね。元々越前の国 今の福井県の出身です
Navi これは後々また出てくる話ですね。
蛭間 そうですね。
Navi 越前から妻沼の方に来たっていうのは何かあるんですか。
蛭間 多分ですね、越前って福井県で、埼玉県と比べて、今は都会ではないと思うんですけど、当時は埼玉とか東京が田舎で福井県が都(京都)に近い都会だったんですね。
Navi なるほど福井は京都の近くですね。
蛭間 実盛は武蔵武士・田舎武士とは違って、ちょっと都会に近いインテリな感じがする武士ですね。越前から来たんだけどそういう都会の感じの方がこちらの方に領地をいただいて、多分頼朝のおじいちゃんの為義から領地をもらったんだと思うんです。
Navi なるほど福井県から埼玉県の妻沼の領地をいただいて、そこを治めている中で、駒王丸を助けるっていうのは何か命のピンチがあったのですか?
蛭間 そうですね結局、駒王丸のお父さん(源義賢)が敗れて、殺されてしまうので子供も殺せっていうふうに見られるんですけれども、そこを畠山重忠のお父さんの重能という人がかわいそうだっていうんで、実盛に預けるっていう話になっています。
Navi 預かりました。実盛公はその後、預かって自分で育てたんじゃないんですね。
蛭間 そうですね。結局みんな周りは敵方になってしまうので、関東にいても危ないだろうということで木曽という長野県の南の方の、山深いところへ連れて行くっていう形になります。
Navi そこだったら安全ということですか。
蛭間 そういうふうに考えたのだと思います。
Navi 木曽義仲になったわけですね
蛭間 そうですね、はい。
Navi 歴史を作ったと思いますね。
蛭間 そうですね。
Navi だって預けるところが違ってたら、木曽義仲じゃなくなるし、生きてなかったかもしれない。これがエピソード第1ということでですね、2歳だったんですね。
蛭間 そうですね。
Navi さて第2のエピソードということで今度は実盛公は今度は源義朝を救うのですね。
蛭間 そうなんです。義朝は為義と、敵対してる方なんですけど、源氏同士で戦い結局ほとんど義朝のものになるなるほど関東の武士はみんな義朝につくように実盛も義朝につくようになるんです。
Navi でも義朝を救うっていうのは、誰から救ったのですか。
蛭間 平氏方からですね。都、京都の方で大きな戦いが二つあって保元の乱と平治の乱と戦いなんですけれども、この平治の乱で源義朝、実盛の仕えている人とですね、平清盛という
Navi 平氏で一番強かったイメージですね。
蛭間 義朝と清盛は平治の乱で激しく衝突しまして結局、清盛が勝って義朝軍が落ちていくんです。本当にその途中で戦いになりまして、そのピンチを実盛が救ったことになり、
Navi すごい!またここの歴史を作ってますね。駒王丸を救い、源義朝を救い。義朝は頼朝のお父さんですよね
蛭間 そうですね
Navi すごいですね。それを救ったあとに第3のエピソードになります。いよいよ長井という熊谷・妻沼の地名が出てきますけど、実盛と長井荘ということで出てきますけれども。ここで、源氏じゃなくなるっていうことですか。
蛭間 そうですね。実盛だけじゃなくて、直実含め周りの武士、みんな大体同じ動きをするんですけれども、今度は平氏の世の中になるので、みんな平氏方になります。
Navi ここで源氏だったらやられちゃうわけですね。
蛭間 生きづらいと思います。
Navi なるほど武士はどっちかっていうと、その血筋というのは関係なく雇われてる感じなんでいいんですね。変わっても
蛭間 変わっていきます。ガンガン変わるし、変わるのがいけないっていうことじゃなくて変わるのが当たり前っていう世の中です。
Navi そして平氏の方になったということなんですね。
蛭間 ほぼ全員平氏になっちゃうんです。
Navi そうでしたか。そしてここで「長井荘」が出るんですけど、こちらの領地は平氏から今度与えられてるようなことになったんですか。
蛭間 そうですね。
Navi 長井荘っていうのは、今の長井小とかあの辺の地区でいいですか。
蛭間 結構広い荘園でして、深谷市の東部から今の熊谷市の北部、旧妻沼町域を含む広い土地でした
Navi そうでしたか。いよいよここで、聖天様が出てきますね。
蛭間 はい、そんな感じでスタートしたんですけど、聖天様は、長井荘、とっても広い荘園を実盛が預かるので、当然領主として、その土地の平和を祈らなくてはいけないので、そのために、聖天様・聖天堂を建てたと実されています。
Navi 聖天堂というっていうのは、お寺・建物を作ったっていうところがスタートなんですね。
蛭間 そうですね。
Navi 何かこのマンガに実盛塚というのが出ていますね。私これ知りませんでした。西野っていうところにあるんですね。これは見に行けば見られると
蛭間 見られます。
Navi そうですか。この本には、どういうところに石碑が残っているとか、経筒の話も出ています。経筒は妻沼小から出土していたのですよね。実盛公と何か関係があるんですか?
蛭間 はっきりと書いてあるわけではないんですけれども、おそらく経筒をここに収めたのは実盛である可能性がとても高いと思います。
Navi そうですか。そしてエピソードの4こめ、実盛と富士川の戦い。私この話を読んだときに、もうこれはなんか笑っちゃいました。これは簡単に言うと。今度は源氏が強くなる場面ですよね
蛭間 そうですね。源氏が勢力を取り戻した後の話になります。
Navi 富士川の戦いは源氏と平氏の戦いでそのとき、実盛公は平氏の方についたわけですね
蛭間 そうですね、そのとき関東武士は、大体、源氏につき始めるんですけれども、実盛は一貫して平家方につくことになります。
Navi そこが義理堅いってさっきおっしゃってたんですか?
蛭間 はい。
Navi ここでも源氏につけば勝てたけど平氏についた。平維盛でしたっけね。富士川で平氏軍として戦うとそこでエピソードがありますね。簡単に教えてもらえますか?
蛭間 そうですね。実盛は、平宗盛の家臣として、猛勇ぶりというか、その戦いぶりもですが、よく知られていて、多分平家軍の中ではかなり強いというイメージがあったと思うんですけれども、維盛が「関東には実盛ぐらい強い武士はどれぐらいいるのか」って言ったら、実盛が「私なんか全然弱くて、もっといっぱい強い弓を引く者がいる。その他に、関東武士は優秀な武士ばっかりで、しかも戦いのときには親が親や子が死んでも、その上を乗り越えていくような戦い方をするから、この戦いは厳しいものになりましょう」ってマンガに書いてあるんですけど、本当はズバリ「勝てません」って言っちゃうんです。
Navi 平氏の人達に言っちゃうんですね。
蛭間 「私はここで討ち死にします」っていう話なんですけれど、
Navi 同じ平氏軍がそれを聞いて、
蛭間 はい、びびってその夜に水鳥が羽ばたいた音で「敵が来た」と思って、逃げちゃうっていう話なんですけど。
Navi ということは、実盛公がその話をしたんで、その情報でみんなびびって、平氏軍が負けちゃったという。
蛭間 そういう話になってます。
Navi すごい。すごいですね、これは。
蛭間 お話なので、多分実際はそうではないとは思うんですが、平家軍が本当に逃げてしまった。水鳥は関係なく、逃げてしまったのは、本当みたいなので、そこから「多分、実盛がいたらこうなるだろう」っていう話を作っていくんだろうとは思うんですけれども。
Navi 実盛公、ストーリーとしてもまた何か歴史を作っちゃいましたね。逃げちゃったっていうのが有名なエピソードですけど。実盛公の言葉で、みんな怖気づいてしまうのは面白いですよ。
蛭間 そうですね。
Navi いよいよ一番のストーリー、5番目のエピソードは、実盛、篠原に散るということで、ここで髪の毛染めた話ですか?
蛭間 そうですね
Navi この戦いは簡単に言うとどんな戦いですか?
蛭間 これはもうちょっと時代が経ちまして、一度飢饉になるので、何年間か戦争がないんですね。源氏と平氏の戦いもこの時代、飢饉が起こると中止になるんですね。兵糧がなくなっちゃうので、そして、また徐々に戦いが始まるんですけれども、まず木曽義仲が、長野から挙兵してどんどん勢力を伸ばしていくんです。それを征伐するために平家軍が大量の軍隊を、北陸とか長野に向けるんですけれども、倶利伽羅峠というところで、平家軍が大敗を期しまして、今度平家が逃げるっていう形になります。篠原というところで、また大きな戦いがあって、結局平家が敗れて逃げていくんですけれども、その戦いで実盛が、っていう話になるんです。
Navi 実盛公はこの戦いを最後だって思ってですね、服を、これはちょっと前のエピソードになりますけどね、よい服、錦の服を着るという話がありましたね。
Navi そうですね。平宗盛から、一番偉い人、大将しか着ることができない「錦の直垂」(にしきのひたたれ)というものがあるんですけれども、「これを着てもいいか」っていうふうに尋ねるんですね。宗盛がそれを聞いて「いい」って許してくれるんですけれども、この時代、今よりもずっと服装とかそういうものに厳しいので、あり得ない処置なんです。
Navi これは派手な 綺麗な服ってことで「錦」っていう。
蛭間 そうですね。錦っていって一番綺麗な高価な布っていうことでね、
Navi 最後の戦いで、本当はおじいちゃんなのに大将でもないのに錦の服をきて、そして最後に散ると、
蛭間 そうですね。もう錦を着ていいっていうことは、もう宗盛が相当実盛を気に入っていてっていう話なんですね。
Navi そうですか。そしてここであの言葉が出てくるのかな。最後死ぬのは先ほど言った福井県出身で福井県だから石川県の近くではい。最後の戦いを迎える石川県と
蛭間 福井県の県境ぐらいで
Navi はいそこで、「故郷に錦を飾る」っていう言葉が出てきて、よくその話聞くんですよ。まさにこの錦の服を着てい死ぬということは
蛭間 そうですね。
Navi これもやっぱり実盛公がらみの話っていうことですかね。「故郷に錦を飾る」って言葉
蛭間 いや、元々の古事だと思うんですけど、その言葉から逆に平家物語が話を作っていったんだと思うんです。
Navi なるほどストーリーがそういう展開に、でもやっぱり実盛公はポイントになってるんですね
蛭間 そうですね。作者はだから宗盛と実盛が近かったっていうことを、このエピソードで示したかったんだと思うんですね。多分それは事実なんだと思います。
Navi そして、出陣する前に、白髪を全部染めて、鏡を見ながら染めてる像が聖天様に、あるんですよね。そして戦って、やられ殺されて首を取られちゃって、取ったときはわかんなかったんだけれども、その髪の毛を洗ってみようということで、洗ってみたら白髪で、実盛公とわかり、木曽義仲は 昔、助けていただいた恩人の実盛公を殺してしまったという悲劇というか、この話がまた伝説になるんですね。
蛭間 そうですね。この話が有名なって、能になったり、歌舞伎の題目になったり、あとは松尾芭蕉が歌にしたりという話になっていきます。
Navi この伝説っていうのが、実はすごい大事なんですね。時代を超えていろんな方々がこの話を語りつぎ残っていく。
蛭間 そうですね。どんどん伝説が成長していく。
Navi 成長?膨れていくっていうか、盛っていくのもあるんですね。
蛭間 どんどん盛っていくことは盛っていくんですけどね。
Navi そうでしたか。
蛭間 はい。
Navi ではここでですね、前半のエピソードが終わったところで曲に行きたいと思います。こちらも蛭間さんからのリクエストで、米米CLUBの浪漫飛行おとどけします。
【 曲 浪漫飛行 米米CLUB】
Navi 時刻は12時39分を回っています。AZ熊谷6階FMクマガヤYZコンサルティングスタジオから、生放送でお送りしている梅林堂提供 やわらか熊谷~僕らがつなぐ物語~第30回斎藤実盛と妻沼聖天山のマンガを基に、お話をしていただいていますけれど、いよいよ後半ということで、私すごく興味があったのはこの斎藤兄弟と平六代っていう話ですけど、斎藤兄弟これは、どんなお話なんですかね
蛭間 平六代という人が、平清盛のひ孫にあたるんですけれども、平家物語の中では嫡流ということになってるんですね。
Navi 嫡流とは?
蛭間 あとを継いだ、繋がっているということで、実際には違ったんですけど、平家物語の中ではそうなっていて、このまだ幼いんですけど、この子が悲劇の人なんですけれども、そのストーリーが結構中心になっていくんですが、それにお供するのが斎藤実盛の息子の斎藤五、六という人物です。
Navi 平家物語の中では重要な人物に、今度は実盛公の息子さんたちが出てくるってことですか?
蛭間 そうですね。
Navi 私、名前がびっくりしちゃって、斎藤五、斎藤六って数字で名前がついてるんですけど。
蛭間 この当時5番目の息子6番目の息子だと思うんですけれども、こういう呼び方をするんです。それほど偉くない人はこういうふうな感じで略されちゃいました。
Navi ここは斎藤兄弟って言ったときには、実盛公の息子なんだということだったんですか
蛭間 はい
Navi なるほど、それでこの2人が悲劇の平六代を守っていくという。やっぱり守るんですね。
蛭間 そうですね。実盛が「守れ」というふうに言うんですね。実盛は先を見通せる武将として描かれてますので、実盛はこの平六代が危険になるっていうこともわかっていて、それでこの斎藤五六兄弟を自分と一緒に戦場に連れていかずに、京都に残して助けようという話なんです。
Navi 平六代を殺そうとしているっていうか、やっつけようとしてる人が頼朝とか北条時政っていうまた歴史上の有名人が出てきて、そういう方々が「どうする?」って話になって。
蛭間 そうですね。頼朝は殺したいと思っているので、それを時政が命じられるんですけれども、ちょっと躊躇するんですね。
Navi やっぱりこういう話って歴史の中に多いですよね。相手を倒そうと思うけど躊躇するっていう。
蛭間 そうですね。
Navi そこが人の心に残る。本当にこの話にも出ているということですね。この本を見ていただけたらと思うんですけども、またここに、いよいよ聖天様との繋がりが出てくる「御正体錫杖頭」のお話をちょっとここに出てますけども、
はい。これはどういう感じで出てくるんでしょうかね。
蛭間 御正体錫杖頭というのは聖天様のご本尊で、一番大事なものになるんですけれども、それを作ったのが斎藤六の子供というふうにされています。
Navi そうでしたか?!これ秘宝で、この間のお開帳で私も見ましたけども、ここからなんですね。
蛭間 そうですね。
Navi そして、7番目のエピソード、今度は歓喜院聖天堂っていうのは、実盛公がなくなる前に作り始めたんだけども再建っていうだいぶ江戸時代までいった話から、今度はスタートして500年?
蛭間 そうですね。実盛が建てて、その後どうなったかっていうのはわからないんですね。次に話がわかるのがこの再建の話になるので、500年たった話です。
Navi 途中何かあったかもしれないけど。
蛭間 そうですね。途中あったんだと思います。ありすぎるくらい。
Navi 資料が出てきたのが
蛭間 そうですね。
Navi そこで人物出てきたのが、今度はですね、大工さんの林正清
蛭間 大工ですね妻沼に住む大工さんです。
Navi ここから林正清さんこれも聖天様を勉強すると必ず出てくるお名前ですけれどもね。そしてあと彫刻うちの石原吟八朗さんですかね。そういった方々が再建に参加して、
蛭間 そうですね。この林正清という人物が、あの総合プロデューサーみたいな感じですね。
Navi そうですか。再建させようとかっていう声を上げたのも林正清さん
蛭間 そうですね
Navi その頃院主様っていうか、院家様もいらっしゃったと思うんですけど、
蛭間 もちろん院主様も信仰の中心なので、この院主様と正清が2人合わさって進めていくって形になると思うんですけども
Navi そして民衆にも声をかけるのはやっぱり 林正清?
蛭間 そうですね。
Navi そうだったですか?大工さんがね。あれですか?林正清さんの夢というかそういったものがあったんですかね、
蛭間 多分すごい強い思いはあったんだと思いますね。
Navi 「再建を実行する」という思いはずっとこの後も続いていくわけです
蛭間 そうですね。
Navi この頃には例の本堂っていうか、奥殿っていうかすごい綺麗なあれができたんでしょうか
蛭間 そうですね。まず奥殿ができるんですね。
Navi 奥殿が先なんですか。いや、僕は今ちょっとこれですごくよくわかりました。そしてその後は8番目のエピソードになると、いよいよ大水害、
蛭間 そうですね。はい。
Navi 妻沼は利根川の近くですから、水害に襲われて、流れちゃうっていうか。そういうことだったんです
蛭間 そうですね。
Navi そしてここで今度は親子っていう下の世代に、今度は繋げていくっていうことですか?
蛭間 そうですね、正清は奥殿だけは、完成を見たんですけど、その後の完成を見られずに死んでしまいますので、その子の正信という人が継ぐことになります。
Navi この水害の間に聖天様の工事がストップしていて、他のお寺を作ったっていうお話が出てますね。
蛭間 そうですね。このときに、聖天堂と同時期に進んでいたとは思うんですけれども、西城の長慶寺というお寺があります。そこの薬師堂というものが、この正清が建てた建物になります。
Navi この正清さんの建てたって言われてる、これがその長慶寺。
蛭間 そうですね。
Navi 長慶寺さん、FMクマガヤの加盟店さんでもあって、これはちょっと見に行きたくなりました。
蛭間 そうですね。彫刻も見事ですので、ぜひ見ていただきたいと思います。
Navi そして正清さんはその悲願は達成できなくて亡くなって、今度は引き継がれたということですね
蛭間 そうですね。
Navi そして中殿・拝殿というところで44年、
蛭間 そうですね。屋根工事も含めると44年もかかるんですね。
Navi そして今度は9こめのエピソード、いよいよ、私も大好きな建物の貴惣門、一番正面というか一番入口のところ
蛭間 山門といわれるお寺の入口の門になります。
Navi この貴惣門っていうのを、ラジオをお聞きの方は、ご存知かどうかわからないんですけど、形が非常に特徴的ですよね。
蛭間 そうですね。横から見ると屋根が三つあるように見えるんですけども、すごく珍しい形なんですよね。
Navi これも、やっぱり林正清の子孫が、建てようという話になってたんですか?
蛭間 そうですね。林正清の子孫が作ることになるんですけれども、洪水のときに長谷川十右衛門っていうお手伝い普請と呼ばれる、妻沼の復旧工事に来る山口県岩国藩の長谷川十右衛門っていう人、この人は「錦帯橋」有名かと思うんですけどこの架け替えを行った名工なんですけれども、この人が建設中の聖天堂を見て「これは素晴らしい建物だ」っていうことで、正清と親交深めるんです。話していく中で、山門はこの聖天堂にふさわしい入口の門の設計図を「私が書きます」っていうことで書いて、それを正清に送るんですよ。
Navi 設計図を?そして、しかもびっくりしたのは山口県からこのお手伝いっていうか。
蛭間 そうですね。
Navi 来るんですね。すごいですね。この長谷川十右衛門さんも名前がよくガイドさんの口からきかれます。
蛭間 はい。
Navi 設計図を見て、すぐできなかったんですよね。
蛭間 そうですね。洪水で聖天堂の工事自体がもう中止されてる状態ですので、とても貴惣門を作るところまでいかなかったんですね。
Navi 洪水で流れってってことですか。でもできてますよね。
蛭間 そうですね、100年後にできることになります。
Navi 100年?!人々が設計図を継いで?いや普通、諦めちゃう感じですけども。
蛭間 正清以来の林家の悲願なんでしょうね。やっぱり聖天様としても、作りたいっていう悲願があったと思いますので。
Navi これはどうしても、貴惣門を作ろうと
蛭間 そうですね。地元の人たちは、聖天堂もそうですけど、地元の人たちがお金を出して作る建物ですので、地元の人たちも協力して、みんなで100年後に作っていくっていう話になります。
Navi そういう設計図から、ずっと作る悲願だった貴惣門ということで、、もうあっという間に時間になってしまいましたけれども。この10番のエピソードまで御紹介できなかったけど、マンガ「斎藤実盛と妻沼聖天山」という本ですが、小学生中学生がいる方は家に必ずありますので、ぜひもう一度見ていただいて、大人もぜひ見ていただいて、そして聖天様を訪ねていただきたいなって思うんですけどね。私は今日このストーリーをどうしてもラジオで伝えたかったのですが、蛭間さんといつかは学校に行って改めて出前授業が何かしたいんですけど、どうでしょうね。
蛭間 そうですね。ぜひやりたいとは思います。
Navi これだけ詳しい蛭間さんに今日、全部話が聞けませんでした。聞いてるだけで今日も勉強になりましたけど、子供たちにわかりやすく、そしてですね、やっぱり斎藤実盛公も、妻沼にプラスして熊谷の街中の人に、もっと知ってもらいたいって思います。
蛭間 思います。
Navi それにはやっぱり蛭間さんの力が必要かなとそれが私の悲願です。ということですねあっという間に時間になってしまいました。ぜひ蛭間さんまた来てくださいね。
蛭間 はいよろしくお願いします。
Navi これから一緒にぜひ出前授業やりませんか、一緒に回りましょう。
蛭間 よろしくお願いします
Navi 妻沼の小学校の皆さん楽しみにしててくださいね。ということで熊谷の皆さんにもね、出前授業できたらと思っています。あっという間に終わってしまいましたけれども今日は、熊谷市史編さん室の蛭間健悟さんに来ていただきました今日はありがとうございました。
蛭間 ありがとうございました。
⏰月曜日 2025.04.28 11:59 · 52mins 熊谷市のマンガ「斎藤実盛と妻沼聖天山」を紹介する生放送
AI要約
要約
この放送では、熊谷市教育委員会が発行したマンガ「斎藤実盛と妻沼聖天山」について、市史編さん室の蛭間健悟氏が詳しく解説しました。蛭間氏は、このマンガが1万6000部印刷され、そのうち1万3600部が小中学生に配布され、残り2400部が市役所や書店で500円で販売されていることを説明しました。漫画は10のエピソードで構成され、斎藤実盛(さねもり)の生涯と、聖天様との関係、そして江戸時代の聖天堂の建設について描かれています。蛭間氏は、斎藤実盛が越前(現在の福井県)出身の武将で、妻沼地域に移住し、平家と源氏の間で重要な役割を果たしたことを解説しました。また、聖天堂の建設と再建の歴史、林正清や長谷川十右衛門による100年にわたる貴惣門建設プロジェクトについても詳しく説明されました。
チャプター
漫画「斎藤実盛と妻沼聖天山」の概要紹介
蛭間氏は、このマンガが熊谷市教育委員会によって3月に発行され、市内の小中学校の児童生徒に配布されたことを説明しました。また、市史編さん室の役割について、古文書の調査や仏像調査、市史の編集作業を行っていることを述べました。
斎藤実盛の生涯と平家物語での描写
蛭間氏は、斎藤実盛が平家物語において知的で義理深い人物として描かれていることを説明し、源平の戦いにおける彼の役割や、最期に髪を染めて戦った逸話について解説しました。
聖天堂の建立と再建の歴史
蛭間氏は、聖天堂が斎藤実盛によって建立され、その後の水害による被害、林正清による再建計画、また、長谷川十右衛門による貴惣門の設計図の提供など、100年にわたる再建の歴史を詳しく説明しました。
インタビュイープロフィール
蛭間健悟(ひるま けんご) 熊谷市史編さん室所属。日本中世史を専門とする学芸員。大学では日本中世史、特に武士の時代を研究。妻沼町(現熊谷市)職員を経て、現在は熊谷市史編さん室で古文書調査や仏像調査、市史の編集業務に従事している。熊谷の歴史や文化財の研究、保存、普及活動に尽力し、特に斎藤実盛や妻沼聖天山に関する深い知見を有する。
本文
【質問】市史編さん室ではどのような業務を行っているのでしょうか?
【答え】熊谷市の歴史書を作成することが主な目的です。具体的には、古文書の収集・調査、仏像や石造物の調査、原稿の編集などを行っています。最近では仏像仏画に関する調査をまとめた本を刊行しました。
【質問】今回の漫画「斎藤実盛と妻沼聖天山」はどのような経緯で制作されることになったのでしょうか?
【答え】熊谷市では偉人をより知ってもらうための漫画シリーズを展開しており、第一弾の「直実・蓮生物語」に続く第二弾として企画されました。斎藤実盛は全国的に見ると直実や畠山重忠と並ぶ偉人でありながら、妻沼地域以外での認知度が低く、より多くの方に知っていただきたいという思いから制作を決定しました。
【質問】斎藤実盛とはどのような人物だったのでしょうか?
【答え】平家物語では知的で義理深い人物として描かれています。越前(現在の福井県)出身で、源氏から平氏へと転じた武将です。特に、木曽義仲を幼少期に救った逸話や、最期に白髪を染めて戦った話は有名です。
【質問】漫画の制作部数と配布状況について教えてください。
【答え】約1万6000部を印刷し、そのうち1万3600部を市内の小・中学生に配布しました。残りの2400部は市役所や市史編さん室、市立熊谷図書館、江南文化財センター、市内の書店などで販売しています。
【質問】妻沼聖天山の再建に関する歴史的な経緯についてお聞かせください。
【答え】江戸時代、林正清という大工棟梁が中心となって再建が進められました。また、山門(貴惣門)の建設では、山口県の長谷川十右衛門という建築家が設計図を提供し、その設計図は100年後に実現することになります。地域の人々の協力と悲願が、世代を超えて受け継がれた象徴的な建造物です。
関連リンク
・マンガ「斎藤実盛・妻沼聖天山」販売場所: – 熊谷市役所 – 市史編さん室 – 妻沼文化財センター – 須原屋書店 – 戸田書店 – 修文堂書店 – 結ぶ堂書店 – 妻沼聖天山 ・埼玉新聞(2024年4月26日付)関連記事
直面している課題
- 斎藤実盛という人物が全国的には直実や畠山重忠と並ぶ偉人であるにもかかわらず、熊谷市内では妻沼地域以外での知名度が低いことを課題として認識しています
- 歴史的事実を伝える際に、客観的な事実と物語としての面白さのバランスを取ることの難しさがあります