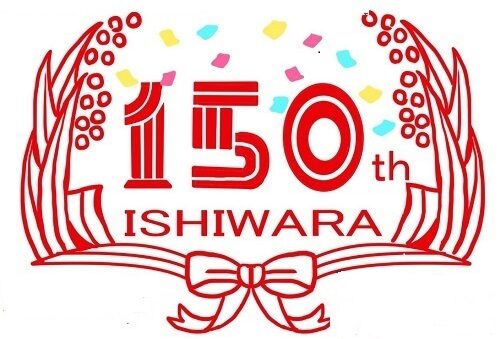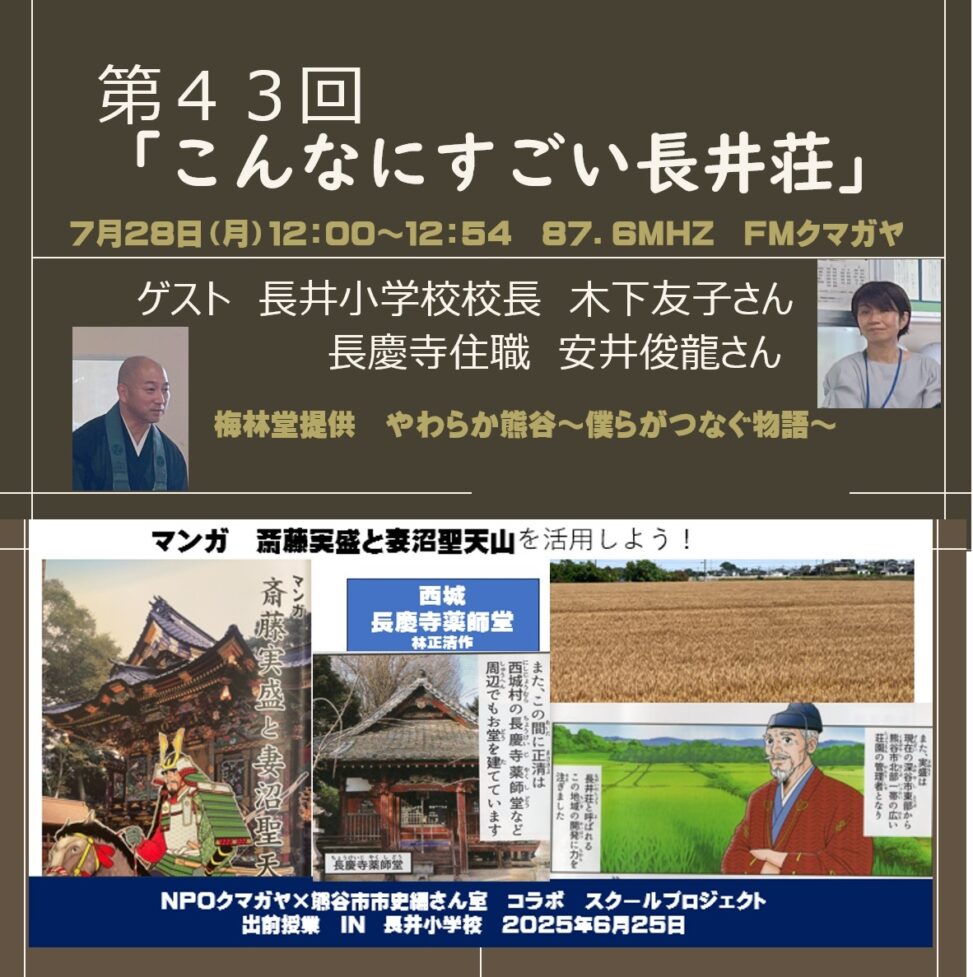7月28日(月)のFMクマガヤ やわらか熊谷 僕らがつなぐ物語は? ゲストに 長井小学校の木下校長先生と長慶寺の安井住職に来ていただきます。 先日 長井小学校でNPO熊谷がマンガ「斎藤実盛と妻沼聖天山」を活用した授業を行いましたが、改めて長井のすごさ、長井荘の豊かさ、そして斎藤実盛公・妻沼聖天山ゆかりの遺稿など長井小と長井の良さを語り合います。
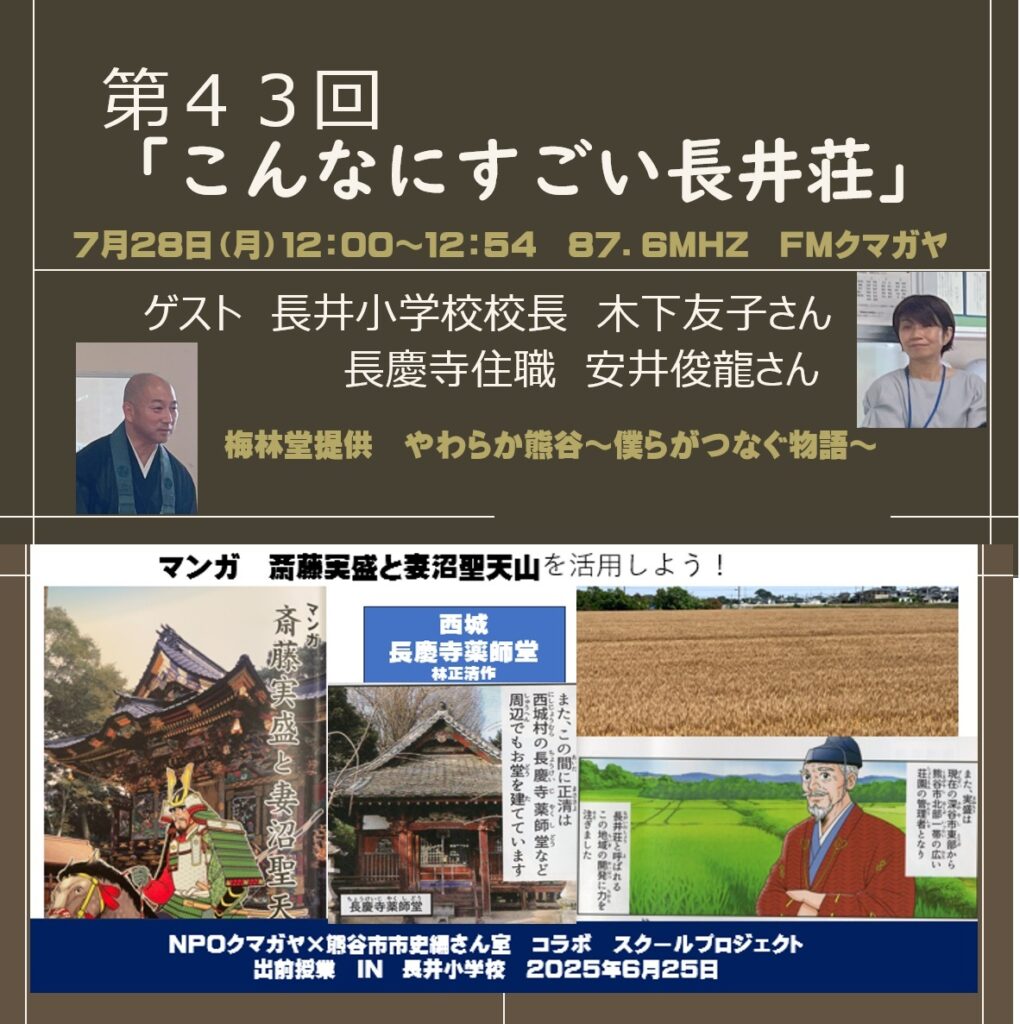
長井小学校校長と長慶寺住職が語る 第43回こんなにすごい長井荘
⏰月曜日 2025.07.28 12:00 · 37mins
AInottaによる文字起こし
Navi 時刻は12時を回りました。AZ熊谷6階FMクマガヤYZコンサルティングスタジオからお送りします。月曜のお昼は梅林堂提供やわらか熊谷僕らがつなぐ物語。今日はですね、第43回こんなにすごい長井荘というタイトルでお送りしたいと思います。ゲストは、なんと熊谷市立長井小学校の校長先生、今日お忙しい中来ていただきました木下友子先生ですこんにちは
木下 こんにちは。木下です。よろしくお願いします。
Navi 長井といえば、そしてFMクマガヤといえば この方、長慶寺住職の安井俊隆さんに来ていただきました。こんにちは。
安井 こんにちは長慶寺の安井俊隆と申します。お願いします。
Navi 加盟店で大変お世話になっております。今日は長井荘ということで長井は荘園なんですよね、歴史の話もするかもしれないし、長井小のこともお話するかもしれないし、長井地区とかね長慶寺さんのお話もっていうこともやっていけたらいいと思うんですけどもね。木下先生。今日はこれからお忙しい仕事があるみたいですけどすいません。その前に来ていただいてということで夏休みなので少し、学校は落ち着きましたか。
木下 はい。でも子供の声がしないのは寂しいです。時々児童クラブに遊びに行っちゃいます。
Navi 校長先生としてもなんですが、教員時代もお世話になりまして一緒にお勤めして、そしてもう立派に校長先生をやっていてということなんですけれども、ご出身はどちらなんでしたっけ。
木下 私自身は埼玉県のあのもうちょっと北にある本庄市で生まれました。教員になってからこちらに
Navi 深谷からだったんですよね
木下 はい
Navi 深谷から熊谷に来て、ずっと熊谷の学校で長井小何年目になりますか。
木下 小学校は実は平成27年、28年と2年間務めたことがあります。そこで安井住職さんともご一緒させていただいたんですけれども。少し間を空けて、昨年度、そして今年7年と2年目になります。
Navi 教頭先生だったでしょ違ったっけ。
木下 教務主任でお勤めしてました。
Navi 教務主任でまた戻ってきたという、長井ご縁があるということなんです
木下 嬉しいです。
Navi いうことで今はお住まいの熊谷ということなんですけどもね。今度は、安井住職。今日は本当にありがとうございます。
安井 よろしくお願いします。ありがとうございます。
Navi 本当に長慶寺はですね、実はチョロチョロ覗きに行って見に行っていたことがあって。最近も行ったんですけどその前にもちょっと妻沼の方に「ここには面白いものがあるよ」って言って、紹介されて覗きに行ったことがありました。
安井 ありがとう。
Navi 空いてるときに今回よく見たのはですね、何でしたっけ林正清さんが作った薬師堂をじっくり見ていきました。
安井 ありがとうございます。
Navi 前回は「本堂の中に何かあるよ」っていうんで。そこに何かあるんですか。
安井 本堂の中も慶応時代に建て直したんですけども。林兵庫正清様と同じ系統の方たちが作ったと言われているので、その薬師堂と同じ時期に作られたというふうに言われていました。
Navi ところで住職はですね。出身小学校はどこでしょうか?
安井 出身小学校は長井小学校出身です。
Navi そうですかそして中学校は
安井 妻沼東中学校です
Navi もうバリバリの
安井 長井生まれの長井育ちです。
Navi 素晴らしい
木下 優秀な人材を輩出中です。
Navi 本当に。いや素晴らしいです長慶寺といえば加盟店さんにもなっていただいて、私がすごくびっくりしたのはまず大銀杏、大銀杏をこの間改めても見に行ったら裏にあるのがそうですか?しめ縄が付いてるやつ
安井 私が住職になってから「大いちょうの長慶寺」と命名して皆さんに知ってもらうようにしました。まあ皆さんに知ってもらうように、それまではずっとあることは知ってるんですけど、昔のあの妻沼郷土かるたの方では、妻沼の大いちょうも知らされて 皆さんに大きないちょうがあるってことは知ってもらいたいので、
Navi とにかくその「大いちょうの長慶寺」さんということで。加盟店さんになっていただいて、ずっと見てて、リポートでもお話をしてたんですけれども、この間の護摩、あの護摩が5月にありました。会った時に私はびっくりしちゃったので、あの銀座のうちわ祭のお囃子をですね、長慶寺でやってるって聞いて、すごい進歩的だなと思っていました。
安い はい、今回初めてねあのお祭りお囃子を、まあ熊谷のお祭りの話っていうのは結構ご縁がいろいろつながって実現したんですけども西城の地元のお祭りっていうのがだいぶ最近やってなくて、やはりこの地元のお祭りのお祭りの感じっていうのかねえ。そういうものもやっぱりあの見習わなきゃいけないのかなと思いまして。トントンと話が進んで、銀座の囃子を境内で演奏して、なんかとてもお祭りっぽくなりました。ありがたかったです。
Navi 新島さんっていう方に、いつもこの番組にも出てもらってるんですけれども、新島さんが「この間長慶寺行ってきたよ」みたいな感じで、言ってたので、えっと思っていけばよかったって思いました。何か長慶寺これから何かが起きるような感じですよ。というわけでこの間も長井小で授業を「マンガ、斎藤実盛と妻沼聖天山」という本を使ってやったんですよね。
木下 やらせていただいたというか、はい、6年生にやったんですよね。
Navi 校長先生、お世話になりました。
木下 6年生に2クラス2回授業していただきましてね。
Navi 安井さんも住職としてきていただいて、大変嬉しかったです。
安井 押しかけてしまったような形になってしまって。まあどうしても長井ということで、様子だけ後ろで見させていたかいただこうかなと思いましたら。関根さんの計らいで、あの皆さんに紹介していただいたという経緯で、本当に恐縮です。
Navi だって、かっこよかったですよね。
木下 はい
Navi 格調高い授業になって、すごく嬉しくなっちゃってテンション上がりました。あの授業は、マンガ画の読み聞かせと。あとは私がちょっと説明したりとかして、あとは子供たちとテストをやったりして、最後に、初級合格証を渡すということで、途中に、マンガ 斎藤実盛と妻沼聖天山の伝説の中に長慶寺が出てくるんですよね。
安井 はい紹介していただきまして、この林正清が作った現存するものの名前がちゃんと出て。長慶寺薬師堂というのは、この熊谷では、妻沼聖天山と私どもと、少し特殊なところの立ち位置にありますので、国宝妻沼聖天山の聖天堂が国宝指定になる、その証拠的なもので、この近隣にも立てていたということは付け添えのような形ではあります。
Navi はい、校長先生、林正清って誰ですか?
木下 林正清さん 妻沼聖天山をまず斎藤実盛公が作った。後に少し時間が経って、「このままではいけないんじゃないか?」と立て直して、立派にしたいという思いを持った。大工さん、宮大工さんでしょうか?というふうに覚えております。
Navi その大工さんが長慶寺を作ったということで、授業の前半は斎藤実盛公の話で、後半は妻沼聖天山のお話でっていう授業だったんですよね。でも、このマンガってたくさん配ったんですけど、調査をしたら子供たちがあまり読んでなかったのです。配っても子供はあまり読んでなかったに加えておうちの人は全然読んでなかったって調査したらわかったんです。本当はこれ、子供たちは当然ですけど、大人も読んでもらいたいですよね。
安井 そうですね、あの販売店とかですね。まあ、熊谷市のホームページの方にも掲載されておりますけども、目の前でもね、あの周文堂さんとか結ぶん堂さん、あとは熊谷の方で取り扱ってるようなんですけども。この読み聞かせを子供たちが聞いて、家で読み上げられるようであれば、もっといいかなと思いますけどね。
Navi そうですよ、どうですか?その授業の後にこれでおうちの人に喋ったんでしょう?
木下 子供たちは授業で聞いたお話を家でぜひおうちの人にもしましょうねということで宿題が与えられましたが、うちの方でも話をした子もいたんではないかと思ってます。
Navi そうでしたか、調査でも6年生保護者は8割ぐらいはこの授業のことを話したってわかっています。
木下 長井の子は真面目なんですよ。素直な子が多くて、だからあのお家へ帰って、このマンガの話を改めてして、そしてね、うちの人もこれをまた読んでもらってね。
Navi 校長先生もこのマンガを読んで、なんか社会科見学を自分でしたって言ってましたね。
木下 あのお恥ずかしながら、長井の地を一度見てみないとなぁと私自身が思いまして、いろいろとマンガに載っている。各地を回らせていただきました。長慶寺さんもお世話になりました。
安井 ありがとうございます。
Navi あとどこ行ったんですか?
木下 あとは実盛塚でしょうか?あと大きな木があの植えられているということで、長昌寺さんお世話になってちょっとお邪魔させていただいたり、あと妻沼西小学校のすぐ近くに、あのいわれのある場所があったので、そこもちょっとお邪魔させていただいたり、ぐるっと回ってみました。
Navi 素晴らしいですね。私は長慶寺さんしかまだ行ってなくて、長昌寺さんにまだ行ってないし、実盛塚がどこにあるかまだ分かんないですけど、ぜひぜひ行ってみたいなって思いますよね。
木下 これ見るとね、面白かったです。
安井 その辺のマップが、熊谷市の教育委員会のデジタルミュージアムの方で、実盛公の史跡のマップが掲載されていますので、そちらにあのどこどこになになにがあるよっていうふうに書いてありますので、参考にいただければ、
Navi これ夏休みの宿題にいいですね。校長先生、どうでしょうですね。
木下 熱中症、気をつけてお出かけください。
Navi 長井小の方々もみんな聞いてると思うんですけれども、ぜひぜひ回っていただいてね。そして、ラジオで出ているあの安井住職さんと、お話ししていただけたらと思うんですけれども、あの住職さん、びっくりしたことがまたもう1個あってですね、はい、なんかこの間の長慶寺に最近行ったら本堂の前にでっかいあの看板が貼ってあって、ラジオ体操って書いてありました。なんですか?あれは
安井 ラジオ体操 地区の子供会でラジオ体操って朝夏休みに入るとやっていたと思うんですけども、それとはまあ、別にあの長慶寺でもラジオ体操をしてみようじゃないかということで、まだ私の子供達が小さかった頃は、小学校に行ってたぐらいの時ですね。境内でもやっていたんですけども、それで20年ぐらいになるんですか。やっております。
Navi もう20年もこれはやってたんですね。
安井 私が50代ですから20年近くやっています。
Navi じゃあ夏休みの風物詩的な感じですかも。
安井 そうですね。子供来てた子供たちはもうね、大きくなっているので、ええ、20年ってことないから15年ぐらいですか、その子供たちにあの夏の思い出じゃないですけど、なかなかね 最初は。1人2人だったんですけど、その後から何年かすると、子供達がえっと結構集まってくれて。それに協賛してくれる熊谷商工会青年部の方達の加盟店、クラブ熊谷に加盟しているような方達も、ご協力いただいて、そしたらその後からえんむちゃんが
Navi そうSNSにえんむちゃんが出てて、えんむちゃんもはいったんですね。
安井 妻沼の商工会キャラクターでありますし、そんな状態でえんむちゃんが来てくれるようになってから一気に子供たちが増えまして、
Navi そうですね、これは素敵でしょうね。私も看板を見てすごいなと思ったんですけど、えんむちゃんが朝から?
安井 朝からきたんですよ。
Navi 6時半って書いてああ、
安井 早起きなんですねー
Navi えんむちゃんはすごい。だから、私はそれを見たときに何かが起きる長慶寺と思いました。
安井 いやいや 住んでる方たちがいるんですけども。集まって、元気な姿を見るっていう機会がないものですから、熊谷うちわ祭とかを中心に、町の方たちが動いてるのと同じように、地域の人が何かを中心に動くってことがないもんですから、お寺に来てもらって、「元気だね」とか、「最近どう」みたいな、そういった会話ができるようなところであれば、いいなと思ってました。
Navi コミュニティーですよね、素敵ですね。こんなにすごい長井荘!っていう感じですね。はいここで、曲をあのかけたいと思います。じゃあ、まず木下校長先生のリクエストでちょっと紹介してください。
木下 私が中学生高校生時代でしょうか?これを聞きながら毎日毎日過ごしておりました。大きな玉ねぎの下で爆風スランプです。
【曲 大きな玉ねぎの下で 爆風スランプ】
Navi 時刻は12時21分を回りました。87.6MHz FMクマガヤ梅林堂提供やわらか熊谷僕らがつなぐ物語「こんなにすごい長井荘」お届けしています。今日は、長井小学校の木下校長先生、そして長慶寺の安井住職に来ていただいてますよろしくお願いします。では、今度は長井小学校のことですか、校長先生、お話いただけたらと思います。どんな学校でしょうかね。
木下 まず、校訓ですが堅い話になっちゃいそうですけど、長井小なので、「な 仲良く が 頑張り、い 一緒に伸びよう。」この校訓のもとに子供たちが毎日元気に登校してきています。素直な子供が多いです。昨年改めて着任して「なんでこんな素直なんだろうな」と思ったところ「地域の方に大切にされてるんだな」っていうところに行き着きました。朝登校一緒に、一緒に学校まで歩いてきてくださる地域の方がいたり、下校の途中で「子供たちがこんな様子だったよ」「挨拶上手だね」なんて褒めてくださる方がいたりと子供たち、さらに大きく、伸びて、そして素直になっていって、こういうところだなって子供たちが素直っていうのは地域の人に守られてた。特別にされてるからだなっていうことを実感しております。良い子たちが多いです。夏休み何して過ごしてるでしょうか?元気だといいです。
Navi という感じで、校長先生優しいですね。本当に、こういうふうに言われたらみんな子供たちは頑張る気になっちゃいますよね。さて長井小学校、その前身っていうか、スタートは、安井住職どんな感じだったんですか
安い 長井小の卒業生として私が実際に言う立場にはないかもしれませんけども、いろいろ明治までですね。いろいろ寺子屋というものが各地域にあったようなのが明治の19年に江波っていう、今長井小がある江波地区の宝蔵院というところのお寺を仮校舎にしまして、江波学校ができまして、そこを中心に、今の長井小学校の敷地へと変貌していきますね。今は福川の支流を挟んだ向こう側に、今長井小が立ってますけどもそれのこっち側、こっちが移ってもわかんないかな。北と東側にありまして今宝蔵院さんがそちらにあるんですけども。だからその辺にも元の長井の役場。長井村役場とかもあったりしてその辺が長井の中心になっていたようですね。
Navi 長井の中心に小学校があったということでよろしいですか
安井 そうですね、周りの学校集まって、子供が通いやすいようにという中学校も一緒に小中一緒だった時代があったとか。最初は長井小学校で、尋常小学校というふうに改称されましてそこが小中一貫でそれから時代を経て尋常小学校とかって言って高等小学校とかいうふうになったとかいうふうなことを聞いたことあります。
Navi 幡羅高等小学校って近くですよね。
安井 そうですね。高等小学校、高等学校ですから高校と一貫なるみたいな
木下 家庭心得というものが有名な 幡羅高等小学校
Navi 熊谷の小学校の先生たちは、みんなそれを大事にしています。幡羅高等小学校から学んで、その道でずっとやってたんですよね。つまり、もしかして長井地区の近くにあった学校ですか。
安井 おそらく明治政府の発令なので、それは全国同じような信念のもとに学校を設立していっているはずですので、同じように高等小学校を卒業してそれぞれに活躍していったんではないかなと思います。県の刊行物も裏表紙に書いてあるんすよ。
Navi やっぱり「こんなにすごいぞ長井荘」ですね。ということで、この間の授業でもちょっとやったんですけど長井っていう地名はないんですよね。
木下 ないですね。字名というか、ではないです。熊谷市長井の字はないです。
Navi 長井村っていうのがあったんですよね。子供たちに長井っていうとこはどこがありますかって言ったらいろいろ言ってましたね。
木下 はい。長井小、長井郵便局 長井公民館があり、農協さんはもう長井ではなく
Navi そうですか。だから長井という地名すごく大事ですよね。斎藤別当実盛さんが治めていたのが長井荘ということで、やっぱり長井の地は改めてこのマンガで、子供たちにはすごい場所だったんだなっていうふうに伝わってるんだと思うんですけどどうでしたか授業を受けて子供たちの反応とか。
木下 改めては、「長井っていう地名がない」っていうことに、まず一つ驚き、でも「自分たちはこの場所に生まれ育って長井小学校に通っている。大切にしなきゃ」っていう思いになった子供が多かったかなというふうに感じています。あと、こんな偉人が出てたんだって聞いたことはある。聖天様に行くと銅像も建てるんだけど、「自分たちの生まれ育ったこの土地にこんなに影響のある方だったんだ。」ってことは、新しく知って、子供たちがこの後大きくなって自分のルーツを見つめたときに、この前していただいた授業って、「大きな足がかりになるな」って思って本当にありがたかったです。
Navi 郷土の偉人って各地にはいると思うんですけどね。全国的に有名な方ですから斎藤別当実盛公といえば、こないだもちょっと授業の中でもありましたけど、歌舞伎とか平家物語のあたりですか。そういったところで残っているということを全国に広めた。あともう一つ。妻沼と生まれた場所「篠原」っていうかあちらの福井ですね。
安井 そちらで元々実盛公は斎藤家に養子に入ってから斎藤さんの姓になるわけですけども、そこの福井の方、私も行ったことありますけども有名なお寺「倶利伽羅不動寺」があって 源平合戦のところでも有名なのが、牛の角に松明をつけて大群が押し寄せてきたっていう、あそこの舞台があの辺ですけどね。
Navi そうですね。だからそれくらい全国に知れ渡っていて、皆さん知っていて 授業でもあったんですけど、文部省唱歌になってたんですよね「斎藤実盛」だから全国の子供たちも歌うぐらいのそういう人の方がいるということでね。子供たちも少し鼻が高くなりましたか。
木下 そうですね。「誰かに話したいな」っていう思いにはなったと思います。それでうちの方にきっと伝わったんだと思います。
Navi そうですよね。この間の子供たちの授業の後アンケート調査をしたら、「やっぱり詳しくなった」っていうこともありますけど、「誰かに話したくなった」っていう子供の割合がうんと増えて、そういうのってすごく大事ですよね。あとはそのマンガの内容ですか、改めて中を見てみると、あちこちに大事な遺跡が残っているっていうのがわかりますよね。皆さん「なぜ残したのか」とか、あのこの間の「銅像を何で作ったのか」っていう答えは、どうでしょうかね。出ましたかね。子供たちに像が残ってるっていうことは、考えてほしいです。熊谷次郎直実公も銅像を作ってますよね。あれ何で作るんですかね、皆さん。子供たちにもぜひ考えてもらいたかったんですよ。
安井 授業の最後のところでちょっと切れがちなところだったですね。回答は宿題ということだった。
Navi そうなんです。宿題です。校長先生どう思いますか。
木下 銅像、そこが象徴になるからでしょうかね。
Navi 銅像残りますもんね、銅像をみると「何だろう」ってなりますよね。伝えていかないと、こういう話って忘れちゃう、ブームだけじゃなくて、定期的に授業して、教えてくれる人が地元の人、授業するのはやっぱり学校しかないのかなって思っちゃって、あとはこのマンガですね。これがいろいろな人に読まれて、それで興味をもってお寺に行って住職さんに「これはどうなんですか」って聞けば、住職さんだって教えてくれるわけだし、学校の先生も教えられるようにそれが一番いいですよね。先生方はどうですか。これを見た感じで
木下 これは昨年度の3月、今年の3月に熊谷市教育委員会が中心になって作ってくださったマンガだったんですが、なかなか手に取って開いて読むっていう時間を職員も持てずにいたのが現実だったので、もう一度手に取った本当にいい機会でした。「うちの学校のことだったけど、よく読んでみたらこんなことがあった。」ていうのを知った子供もですけれども、先生方も多かったということです。
Navi 先生方は、結構これを勉強してから教えるっていうのはなかなか大変だと思うんですけど、子供たちと一緒に触れて、それで改めて「聖天様はすごいな」とか「実盛公がすごいんだな」って、感じてくれればいいのかなと思います。私も実は全然知らなくて、たまたま妻沼小に行って、こういうことを知り、初めて興味を持ったのです。私も木下先生も理科の教員ですからね。
木下 そうなんですよ。
Navi なのに何か今は気がついたら歴史のことをやっています。どうですか。知れば知るほど好きになってきたでしょ。
木下 面白いですね。
Navi そうだから、社会の先生は元々みんな知ってて詳しいんですけど、自分なんかは理科で実験とかそういうのが大好きだったのに気がついたら、何か「斎藤実盛公」とか、「直実公」とか、そういうところに惹かれて、夢中で勉強してたんですけども、やっぱり学校にとってこれ大事ですよね。
木下 はい 時間の流れですかね、理科も面白いんですけれども、でも、時間を経ても残っているものに意味がある。先ほどの話じゃないですが意味がある。意味を持たせる。そこに発見がある。面白いんでしょう。ロマンだなと思います。
Navi はい こういう感じの事を聞いて教員もこのマンガで結構、乗ってきてるところがあるんですけど。
安井 そうですね。私の個人的な感想ですけども、マンガになったっていうことが大きいと思うんです。文字で読んでるっていうのはなかなか目に触れないですし、熊谷市の市史編さんの熊谷市史にもたくさん資料と文が書いてありますけども、それを手に取るっていうことはまずないですね。もちろん銅像があって象徴的なんですけども、そこ行ってことありますか。
Navi はいあります。
安井 銅像のところにボタンがあります。音の昼間はボタンを押すと、さっき「実盛慕情」が流れるという。あの装置、あそこにあってもなかなか触れる人もいないんです。ですから、マンガになってビジュアルになって、そうすると。とても親近感がわいて、昔、生きてた人なんだなっていう実感がわくと思うんです。私もそうなんすけども、文章が読めない体質なので、文字とかよりも耳で聞く方がすっとわかる理解できるっていう人は多数いると思うんですよ。もちろんとっつきやすいですから。そういった意味では、歴史上の人物の本に書いてある登場人物、多分昔は 能とか歌舞伎とかもビジュアルで伝えるものの役割があったと思うんですね。そういう意味では意味ではこのマンガになったら、実在のこの地域に活躍した人なんだねっていうのが、子供たちにも大人にもすっと入ってくる内容だったと思います。そしてそれを尋ねてみようっていう機会にもなったんじゃないかな
Navi そうです。訪ねてみようっていうのをこのマンガを見て、林正清の話を妻沼聖天様のときに聞いてたんですけども、行ってみたらやっぱり彫刻ってすごいんですよね。
安井 そうですね。これを機会に、今実盛公の銅像を、実際見ていただきたいと思うんですね。雄姿ですよ。髪を黒く染めて年寄りだと侮らないように、これは実際に自分がどこの誰だと明かさずに主を逃がすっていう役割に徹するっていうところの物語が、さっきの実盛の能であったり、直垂を垂らして故郷に錦を飾るっていう、その錦を飾った福井県のところで討死するわけですけども、そのところの銅像繋がりでちょっと知ってほしいのは、その福井で討ち死にされたところでは、その木曽義仲が首実験をして、「これは、誰だと。」その首を見て、もしかしたら実盛かもしれないっていう情報で髪の毛を洗ったら白髪の実盛の首だったという。このシーンが福井県の銅像にあるんです。
Navi はいありますよね。
安井 これは本当にその涙する義仲と、手塚、何でしたっけ。
Navi 手塚光盛
安井 光盛がそれを悲しんでるというそのシーンは妻沼とセットなんですよ。
Navi そういうのも含めて妻沼の方はそこの地域に行くツアーみたいなので行ってる人もいるみたいで。それはすごいなと思っています。行ってみたいなって思います。
安井 そうですね。妻沼聖天山界隈の方たちは実盛敬仰会という会を作ってずっと実盛のことを、啓発しておりますけども、そんな中でも、お互いに向こうの兜神社 「無惨やな。兜の下のキリギリス」の兜を奉納した神社さんとか、先ほどのところにお互い交流を続けております。
Navi 本当に実際に見に行くっていうのは、楽しみですよ
木下 行ってみたいですね。
Navi さて、ここでまた今度は曲にいきたいと思います。今度は安井住職さんのリクエストですけどご紹介をお願いします。
安井 先ほど高校時代といいますの高校に通ってるところにレンタルショップ・CDショップがあって、そこにずっと通い、いろいろとダビングをしてそんなときに聞いていた一番の世代の曲です。はい。大江千里でYOU。
Navi お届けします。
【曲 大江千里 YOU】
Navi 時刻は12時41分を回りました。87.6MHz FMクマガヤ 梅林堂提供 やわらか熊谷 僕らがつなぐ物語「こんなにすごい長井荘」をお届けしています。長井荘はすごいっていうか、長井荘に限らず、この近くで長井の近く妻沼も含めていろんなことがありますよね。この間先ほどちょっと話題が出たんですけど、あばれ神輿実は初めてみて来たんですよ。すごかったです。
安井 そうですね「葛和田」という地区にある大杉神社の祭礼の夏の風物詩「あばれ神輿」という名前で、出来島のあばれ神輿と、この葛和田のあばれ神輿二つですね。夏には行われる。
Navi びっくりしました。こういうんだなと思ってあの水の中で水かけっこするかと思ったら違いますね。お神輿の上に登るんですね。
安井 登ってそこで威勢のいい 若い衆の度胸試してなんて言うんでしょうか。それともたくさんお祭りのにぎにぎしくすると、神様も喜ぶっていうことからもよるんでしょうけどもその屋根から川面に飛び込むというのいうところをよく写真に撮られているのを見たことがあります。
Navi 飛沫が上がってるんで水かけてるかと思ったらね。そこから落っこちるっていうかっていう
安井 神輿をもみ洗いしてその水で清めて神様が元気になる。よみがえるというような、
Navi すごい文化だなって思って。いろんなことが知らなかったんですけども、私もその出身はこちら熊谷なんですけれどもいろんなところを知ることができて、こういうのもあるんだと思って。先日その麦の秋っていう春に麦が茶色くなるところの写真を撮りたいなと思って長井地区に行ったらほんとに素晴らしい風景でした。
木下 もう麦秋みごとです。麦の上を風が渡る姿が本当に風流です。子供たちも麦の後には田んぼになるっていうのもよくわかっていて。どの子に聞いても麦の次は次田んぼって言いながら、ただの麦は本当に見事で、本校東側だけ川が流れているのですが、その他三方が全部麦畑で、
Navi その麦の風景を見たときに、なんか昔の長井の豊かな土地っていうのをちょっと、大昔を想像できるような風景だったんで、素敵だな
木下 ありがとうございます。
安井 長井荘って荘園ですから 元々条里制こちらに米の取れ高っていうことがその国の財力になりますから。ということで、麦はその後なんですけども米をたくさん作った風景っていうのは、条里制ですから 奈良時代とか平安時代から変わらず、この辺が開けた象徴でもありますし、長井荘の象徴が先ほどの田園風景 麦畑ができたのは麦王の影響でしょうけども二毛作が始まってからのことだと思いますけども、その田園風景っていうのは、その長井の土地を開かれた当時からあるものだというふうに思われるんですね。
Navi いや本当に広がってると昔の武将とかがそういうところを 治めて立って眺めてるのかなって、このマンガにも出てくるような風景が今でも残っているのを、見て素敵だなっていうふうに感じました。長井は特別です。
安井 お子さんたちもその校舎で学んだ風景っていうのを覚えてらっしゃるんじゃないですか。
木下 そうですね。はい。でもそれが本当に自然にもう自分の体の中に染み込んでいるので、それが当たり前なんだと思います。
安井 もっと価値がわかった方がいい。もうね、ただ改めて
木下 私が世話になっている方の1人に「長井で生まれ育ったんだよ。卒業生なんですよ」っていう方がいらっしゃるんですが、その方に「長井って、この後さ」っていう話で「いやああんまり変わって欲しくないんだよね」っていう声が返ってきたりします。「子供の頃にトラックの後ろに乗せてもらって学校帰ったとか。」「カエル捕まえてどうだこうだ」とか。
安井 時効ですね。
木下 そんな話を伺いました。
安井 私も載せられた。長井小はヘルメットかぶってるから、ぎりぎり大丈夫かもしれません
Navi いやなんかすごいですね。今では見られない風景ですけど
木下 そうですね
Navi なんか映画に出てくるようなね。
安井 子供がね、暑い人は下校とか、ぐったりしてるんですよ。ですから私なんかもそうなんですけど、近くの床屋さんによって水をもらって帰る。そこの井戸水をくんでくれるのでその水が冷たくて美味しいというので、なかなか子供が帰ってこないっていうんで、迎えに来られたことありますよ。うちの子供もそれをやってましたから
木下 長慶寺さんでも水いただけてなんていう話も入ってます
安井 昔は 水が井戸水っていうのは、地下水?をくんで飲んでたんですよ。今では考えられないんですけども、そういうところに美味しい水がありまして、子供たちはよく知ってるんでそこでみんな休憩して帰る。
Navi だって井戸水は冷たいですもんね。そうです今長慶寺さんの話が出たのでね もうちょっとアピールしていただけたらと思うんですけどね。
安井 私どもは長井の中でも一番南側にある西城地区というところにあって、西城はなら熊谷市の奈良と境になってるところですね。ですから長井という一番長井荘でいうところの日向とか、この辺ですね。一番東の外れに近い方ですね。位置関係が
木下 近くに福川がながれていて
安井 そうですね。福川は利根川の支流になっているよう今先ほどの稲麦の用水にも使われている福川がすぐ裏にありまして、この福川もたどれば向こうの深谷の唐沢川とかあちらの方と同じで、支流になってまして、元は長井小の横から通ってるんですけど、弥藤吾の観清寺とかあっちの方ですよね。今はイールから1回観清寺の方に行きまして、そこから長井に来て長井の横を通って江波、それで西城の横から直角に曲がって中条堤の方に落ちるっていうところにあります。
Navi なんか福川もお話があるみたいですね。さっき亀の話ですか。
木下 亀の話。
Navi 自慢じゃないですか
木下 そうですよ。
安井 「熊谷の昔話」というと図書館に行けばご覧になれると思いますけど。
Navi そちら持ってきてもらったんですけども
安井 長慶寺時の縁起。江戸時代に書かれた縁起の中にも同じ内容で書かれています。大体内容は同じなんですけども、江波とその西城の間を流れるその先ほどの福川、福の川と書いた福川にお金持ちの家があって、そこに勤めてた女の人
名前を福さん「おふくさん」と言う人がいて、そこのお金持ちの人が馬で村じゅうを駆け回って、福川のところに来たところで、馬の尻尾に亀がくっついてきてしまったと。すごい力で離さないので屋敷まで連れて帰ってきちゃったらぐったりしてしまったので、そのお福さんが水をかけてあげたという。そしたら元気になって、その捕まえて縄をちぎって福川に戻っていったというところに、勤めてたお福さんが洗濯とか、一説にはちょっとつらい事があって川に泣きにいってたこともあって行って、その亀がキラキラしてるものをくわえてその福さんに与えていった。川に行くたびにもらってたんでお金が貯まったので家に帰って両親とともに幸せになったというような伝説があります。
Navi なるほど、福川と
安井 福川も福をもたらす川なのか、福さんが故の川なのか2つ説があります
Navi なるほどね。
木下 今も亀はいるとか、
安井 亀はですね。日本の在来種のクサガメとかもおりますし、我々の時代は縁日でよく見るミドリガメ逃しちゃった
のかな、ミシシッピアカミミガメも多少見られますけども、ただ、うちに来るのはクサガメもミドリガメも来ますので、それで藪を見つけてそこに亀が卵を産みに行くんですね。今言ったように5月から6月
Navi それすごいじゃないですか。
木下 学校に子供が持って帰ってきちゃったことがありまして
安井 普通に亀が道を歩いてるんですよ。
Navi 亀が?
木下 「通学路にいた」とかって言って子供が持ってきました。
Navi なんだか長慶寺にはカブトムシがいっぱいいるって噂話してましたね
木下 この前行ったら、3年生の子供がちょうどいて、はい、カブトムシ取りに来るんでお父さんとして
Navi これがいいですね ちょっと時間になっちゃってる。後になってからゴロゴロなんて話が出てくるんですか。
木下 子供にとってもワンダーランドです
Navi 本当に素晴らしいところだなっていうふうに思います。彫刻は改めて見に行っていただいたりしたほうがいいです。なんかまだいっぱい長慶寺さんにはあるようです。
木下 十二支がまわっているような
安井 林正清さんが棟梁として作ったお堂として先ほどご紹介しましたけども。、林兵庫正清を棟梁に、石原吟八、板坂伊平次、新井孫四郎などの彫刻家が作った薬師堂が現存しています。建てたのは享保18年に棟上げ完成がされている。そういったお堂が江戸時代、
Navi 享保だって、享保の改革じゃないですか!
木下 享保の改革
安井 聖天様の洪水があって、お金を集めてる最中、1回ここ長慶寺で作られたものが、薬師堂にあって、その後聖天堂奥殿建設が開始されているというふうに、
Navi いやもう どんどんザクザク出てきちゃった。本当はもう時間になっちゃって終わり、まだありそうなのでね、また来てくださいね。
安井 はい。よければまた呼んでください。
Navi というわけでね、たくさん「こんなにすごい長井荘」「長慶寺」そして「長井小学校」というお話をしていただいたんですけど、今日は長井小学校の校長木下友子先生そして長慶寺住職 安井俊隆さんに来ていただきました。ありがとうございました。
一同 ありがとうございます
Navi 本当にまた来てくださいね。
一同 よろしくお願いします。